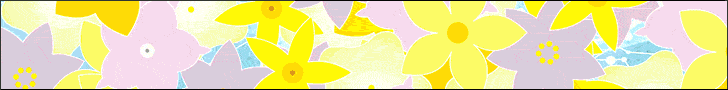農薬:防除学習帖
【防除学習帖】第19回 害虫の防除方法(化学的防除・3)2019年9月20日
害虫の防除方法において最も一般的な防除法は化学的防除(農薬による防除)だ。農薬は、その有効成分によって害虫に作用するポイントが異なり、その作用ポイントによって様々なものがある。前回までに、害虫の神経やエネルギー代謝系に作用する殺虫剤を紹介した。今回は、その他いくつかのものを紹介する。
(5)アセチルCoAカルボキシラーゼの活性を阻害するもの
害虫の身体はたくさんの細胞で形作られており、生育の際には、細胞分裂などをしては絶えず新陳代謝を繰り返している。細胞分裂によって新たに細胞がつくられる時、細胞膜の構成成分である脂質も多くつくられる。
アセチルCoAカルボキシラーゼは、害虫の体内で脂質をつくるために重要な役割を果たしている酵素。殺虫剤の成分がこの酵素の活性を阻害すると、害虫は脂質をつくることができなくなり、脂質が主な構成成分である細胞膜をつくれない。この結果、正常な細胞分裂ができず、生育ができずに死に至る。
この作用を示す殺虫剤は、テトロン酸・テトラミン酸誘導体(商品名:ダニエモン、ダニゲッター、モベント)である。
(6)消化器系に作用するもの
カイコ卒倒病の原因細菌であるBacillus thuringiensis(略してBT)がつくる結晶タンパクを有効成分とするもの。この結晶タンパクは、アルカリ性であるチョウ目害虫消化管に入ると食毒を発現し、腸管の細胞膜に作用する。この結果、害虫は敗血症を起こし、死に至る。
この作用を示す殺虫剤は、BT剤(商品名:エコマスターBT、エスマルク、サブリナ、ゼンターリ、トアローCT、バシレックス、フローバック)である。(特性等はVol.13 生物的防除Ⅰを参照のこと)
(7)非特異的に酵素活性阻害するもの
害虫の生命活動には様々な酵素が働いているが、それらの多くは、SH基や、NH2基、OH基といった反応基を持っている。これらの反応基に殺虫剤などが反応することで、酵素が正常に働くことができなくなって、結果として害虫は死に至る。これらの反応基の複数に反応する殺虫剤を非特異的酵素阻害剤といい、害虫の多くや害虫以外の生物にも影響を与える。
この作用を示す殺虫剤は、土壌消毒剤であるクロルピクリン(商品名:クロールピクリン、ソイリーン(混合剤))がある。
土壌消毒剤は、土壌中に殺虫剤を注入するなどしてガス化させ、土壌中の害虫や病原菌、雑草などを駆除するために使われる。土壌消毒剤を使用する場合には、防毒マスクや防除衣を着用しての処理が不可欠で、一定の消毒期間をおいて、ガス抜きを行うなど、使用上の注意を確実に守って使用する必要がある。
4.化学的防除(農薬)の効果を最大限に引き出すために
殺虫剤は、害虫の皮膚や口、気門などから害虫の体内に入り効果を示す。このため、殺虫剤の効果を高め、安定させるためには、いかにして害虫に取り込ませるかが重要だ。
そのための注意点を何点か整理してみた。
(1)皮膚や気門などから入る殺虫剤の場合
害虫の皮膚や気門などから殺虫剤を取り込ませる場合は、とにかく害虫の身体に殺虫剤がかかるように、害虫目がけて丁寧に散布する。特に気門封鎖剤の場合は、気門に殺虫剤がかからないと効果がないので、害虫のいそうなところ目がけて丁寧に散布する必要がある。粗く撒くと、散布ムラができ、ムラのあったところにいた害虫は生きながらえることになる。 土壌線虫防除のための粒剤(ネマトリンエースやネマキックなど)は、土壌中にある殺虫剤とセンチュウが接触してはじめて効果を示すため、殺虫剤に触れる機会を増やすために、土壌の中に均一に分散するよう丁寧に混和する必要がある。
(2)口から入る殺虫剤の場合
ほとんどの殺虫剤がこの作用を持つ。殺虫剤を害虫の口に入れるには、害虫が食害しそうな作物の部位に殺虫剤を散布し、殺虫剤の均一な被膜を作る必要がある。浸透移行や浸達性のある殺虫剤であれば多少の散布ムラがあっても作物の体内に浸透し、害虫を迎え撃ってくれる。
しかし、浸透移行性の無い(少ない)殺虫剤の場合は、とにかく丁寧に散布して、隙間のないように殺虫剤の被膜をつくることが必要。散布剤の散布は、丁寧に均一にが基本中の基本だ。
この点、粒剤の場合は、用法・用量を守って確実に散布しさえすれば、作物の根から吸われて作物の全身に行きわたるので安心。ただし、粒剤の散布量が少ないと、作物の全身に行き渡る量が少なくて効果にムラが出たり、多すぎると残留の問題や薬害の発生懸念があるため、粒剤は用法・用量を確実に守る必要がある。
(3)雨が降ったり水滴があるときは散布しない
水和剤や乳剤、フロアブルなどの水に希釈して散布する殺虫剤の場合、雨が降ったり朝露があったりで、作物表面が濡れている場合は散布しない。作物表面に水滴があると、せっかく散布しても薬液が流れてしまったり、薄まったりして、殺虫剤が十分な効果を示すための薬量を十分に付着させられなくなるからだ。
同様に、薬液が乾いていない散布直後に雨が降ったような場合にも、薬液が流れ、十分な効果を発揮しなくなる。そのような場合には追加防除が必要になるので、農薬散布前後は、天候をよく確認して、散布スケジュールを決めるように心がけたい。
(4)太陽光と温度の影響も考慮
農薬散布は基本的に朝夕の涼しい時を狙って行うのが鉄則だ。カンカン照りの中で散布すると、作物や散布者自体も参ってしまうが、撒かれた殺虫剤も強い太陽光で分解が促進され、効果が低くなったり、長続きしなくなったりする場合があるのだ。また、温度が高い時も、作物の薬害を助長したり、散布者へ熱中症などの被害を起こす恐れがある。
本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
【防除学習帖】
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日
シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日 -
 農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日
農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日 -
 スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日
スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日 -
 【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日
【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日 -
 新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日
新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日 -
 「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日
「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日 -
 鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日
鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日 -
 米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日
米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日 -
 (465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日
(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日 -
 VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日
VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日 -
 いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日
いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日 -
 「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日
「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日 -
 生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日
生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日 -
 「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日
「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日 -
 【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日
【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日 -
 福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日
福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日 -
 冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日
冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日 -
 宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日
宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日 -
 なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日
なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日