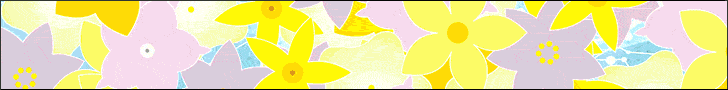農薬:防除学習帖
農薬の上手な施用法3【防除学習帖】第83回2020年12月25日
前回までに農薬製剤には、用途や使用方法によって様々なものがあることを紹介した。では、なぜこんなにたくさんの製剤があるのか?
1.なぜ製剤が必要なのか
農薬は、有効成分が対象とする病害虫雑草に接触してはじめて効果を発揮するので、本来であれば有効成分を均一に散布すればいいことになるが、一般に農薬の有効成分の10アールあたりの投下量は多くないので、均一に散布することは難しい。
例えば、有効成分を20%含むA水和剤を1000倍希釈で10アールあたり300リットル散布する場合、A水和剤の有効成分が10アールあたりに散布される量はどの位になるか計算してみよう。
A水和剤の1000倍希釈液(散布液)を300リットル作るときにA水和剤製剤の必要量は、次のような計算によってわかる。
(1) 300リットルの希釈液のグラム数は、300(リットル)×1000(1リットルは1000g)=30万(g)
(2) 1000倍に希釈するために必要なA水和剤の製剤量は、30万(g)÷1000=300(g)
(3) A水和剤300gに含まれる有効成分量は、300(g)×0.2(20%)=60(g)
つまり、A水和剤の場合は、原理的には10アールあたりに60gの有効成分を均一に散布することができれば効果を発揮することになる。
ところが、10アール(=1000平方メートル)あたり60gということは1平方メートルあたり0.6gとなり、1m四方の面積に0.6gの有効成分を均一に散布することは無風状態でやってもかなり難しい。ましてや、作物が栽植されている場合は、作物体全体に均一に散布することは、作物自体の表面積が増えるためさらに難しくなる、いや不可能である。
このため、多くの農薬は有効成分にキャリア(増量剤)に有効成分を均一に混ぜて、均一に散布しやすい(できる)ようにしてある。
この増量剤には、界面活性剤や粘土鉱物などが多種類あるが、それらを有効成分の性質や用途に合わせ、有効成分の効果が最大限現れるように、色々な組み合わせを試したりしながら最適な製剤が作られていく。その結果、たくさんの製剤が存在するようになった。
2. 製剤に求められる性能を整理してみる。
(1)均一に散布しやすくすること
少量の有効成分を均一に散布できるようにでき、既存の防除器具が使えるものなど
(2)防除効果が最大限になること
少しずつ有効成分を放出して残効性を向上させたり、有効成分が染み込みやすくすることで、作物内部に潜む病原菌に効果を表すことができるようにする、有効成分を作物表面に長く留めて長く聞かせるなど
(3)薬害を回避すること
有効成分によっては、作物に障害(薬害)を起こすことがあるので、それらが起こらないように、薬害軽減剤などを添加するなど。
(4)散布者や作物、環境に安全であること
薬剤調整時に粉立ちせず、粉塵を吸い込んでしまうことが無いようにする、農薬成分に直接触れることなく散布できるものなど
(5)長期間の保管に耐えられること
農薬の有効成分の期間(3年~5年)に、一般の保管状態で、有効成分が分解・消失することなく効果を保つことができる、変質したり希釈性が変化したりしないなど
(6)散布労力が軽減できること
散布労力・散布時間を短縮できる(ジャンボ剤、流し込み製剤など)
3.製剤と施用法
農薬は、作物、対象病害虫草毎に使用量、希釈倍数、使用方法、収穫前使用日数、総使用回数などを定めて、国の登録を受けている。現在、国内では農薬登録を取っていないものを防除目的で使用してはならないことになっている(在来天敵、重曹や食酢など一部の特定防除資材を除く)。
農薬取締法では、農薬登録内容を遵守して使用することを義務化しており、違反した場合、懲役や罰金刑も課せられる。このため、農薬の散布者は登録内容を遵守しながら使用しているのであるが、散布の仕方によっては、ドリフトを発生させ、加害者にも被害者にもなることがあるので注意が必要だ。
(1) 加害者になる場合
農薬にはそれぞれ登録内容があり、使用できる作物が決められている。登録されている作物以外に使用すると、「適用外使用」となって農薬取締法違反となる。
どんな時に起こるかというと、農薬登録内容に変更があって登録作物が削除された場合やドリフトである。前者については、有効期限内の製剤に添付された農薬ラベルを確認することで回避できるが、後者のドリフトについては、農薬散布時に十分な注意が必要だ。
水希釈剤や粉剤を散布するとき風が強かったりすると、薬液や粉体が隣接の作物に飛散して付着してしまうことがある。この時、飛散した農薬が隣接の作物に登録がないものであれば、適用外使用となって、飛散を受けた作物は販売できなくなる。この時、農薬の散布者は、ドリフトによって隣接の作物による収入が得られなくなるという被害を起こすことになり、加害者となる。
(2)被害者になる場合
(1)とは逆に、自身は散布していなくても、隣から飛んできた農薬が自分の作物にドリフトして付着した場合、その農薬が自分の作物の登録が無ければ、農薬取締法違反となって販売ができなくなる。この場合、ドリフトによって自分の作物による収入が得られなくなるという被害を受けることになるので、被害者となる。
このように、農薬散布をする場合、飛散(ドリフト)による被害者にも加害者にもなり得ることをよく理解しておく必要がある。この時、飛散に大きく関与しているのが製剤である。次回、飛散のメカニズムと回避の方法について整理したい。
このシリーズの一覧は以下のリンクをご覧ください
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日
【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日 -
 【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日
【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日 -
 全中 新会長推薦者に神農佳人氏2025年12月16日
全中 新会長推薦者に神農佳人氏2025年12月16日 -
 ひこばえと外国産米は主食用供給量に加えられるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月16日
ひこばえと外国産米は主食用供給量に加えられるのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年12月16日 -
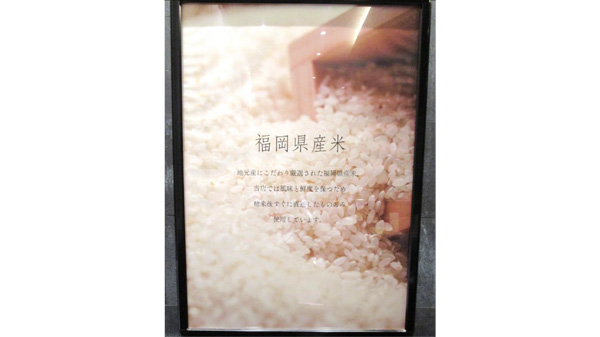 米トレサ法で初の勧告措置 「博多天ぷら たかお」が米産地を不適正表示2025年12月16日
米トレサ法で初の勧告措置 「博多天ぷら たかお」が米産地を不適正表示2025年12月16日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日 -
 「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日
「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日 -
 「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日
「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日 -
 米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日
米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日 -
 【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日
【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日 -
 北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日
北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日 -
 全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日
全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日 -
 Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日
Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日 -
 国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日
国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日 -
 農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日
農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日 -
 農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日
農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日 -
 7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日
7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日 -
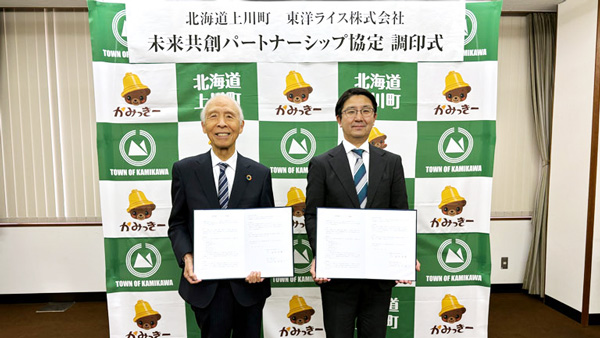 北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日
北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日