農薬:防除学習帖
トマト病害虫雑草防除のネタ帳 不完全菌類の防除⑧【防除学習帖】第180回2022年12月17日
現在、防除学習帖では病原菌の種類別にその生態や防除法を紹介している。前回に続いて土壌伝染性の不完全菌類病の防除ネタを紹介していく。
1.トマト半身萎凋病
(1)病原菌
不完全菌類に属する Verticillium dahliae という糸状菌(かび)である。
(2)生態と被害
感染すると、はじめ下位葉の小葉が部分的にしおれて、水が切れた時のように葉の縁が巻き上がる。後に葉縁が変色し、小葉全体が黄変、最後に褐変・枯死する。その後、順次上位葉が同様に発病・枯死していく。このような症状が片側のみに偏って発生することがあるため、半身萎凋の名前が付いたと言われている。葉の機能が著しく奪われるため、発病株は生育不良に陥り、草丈が低くなる。葉柄や茎の導管部は黄褐色に変化し、根も褐変する。
被害部の内外には微小菌核を形成して土壌中で越冬し、翌年作物の根の先端部や傷口から侵入し発病する。定植1か月後から収穫期末期まで栽培期間を通じて慢性的に発生する。
22~25℃の比較的高温で湿潤条件で発生が多くなる。
本病の微小菌核は土壌中で10年以上生存するため、萎凋病同様に、一度発生すると伝染源が長年残るので厄介な病害である。
(3)防除法
①抵抗性品種・台木の利用
本病抵抗性品種や抵抗性台木を使用した接ぎ木苗での栽培を行う。
②輪作
ほとんど侵されることの無いイネ科作物との輪作が効果は高いが、微小菌核の生存期間が長いので、輪作期間は長くとる必要がある。可能であれば、時々水田化すると抑制効果が高くなる。
③有機物の施用
有機物の施用は、土壌の物理性を改善し、土壌微生物の多様性を増すことで病原菌の密度を下げる効果がある。本病の場合も、堆肥(完熟)、バーク堆肥、鶏糞、稲わらで病害発生の軽減効果が認められている。
④石灰の施用
酸性土壌で発生が多くなるので、消石灰など石灰質資材の施用して酸性土壌をアルカリ側に矯正することにより発病を抑えることができる。
⑤湿度を下げる
湿度が高いと発生が多くなるので、ほ場の排水をよくし、風通しをよくして湿度を下げる。
⑥窒素肥料を多用すると、葉色が濃く、作物体が柔らかくなるので発生が多くなるので、土壌診断にもとづく適正施肥を心がける。
⑦根が傷むと菌が侵入しやすくなるので、根いたみの原因(湿害、干害、塩類集積、土壌害虫の被害、土壌センチュウの被害)を避けるよう管理する。
⑧発病した被害作物をほ場に残したり、すき込んだりすると菌の密度が増して発病が多くなるので、それらは可能な限り速やかにほ場の外に出して適切に処分すること。
⑨土壌消毒の実施
【太陽熱消毒】
十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。
病原菌は、およそ60℃の温度で死滅してしまうため、原因病害虫の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。
【土壌還元消毒法】
この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間がおく必要がある。また、近隣に住居があるような圃場では臭いの発生に注意が必要である。
【蒸気・熱水消毒】
文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60℃にまで上昇させるかが鍵である。この方法を実施するには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須である。このため、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。
【土壌消毒剤】
土壌消毒剤(クロルピクリン剤、ディトラペックス剤、カーバムナトリウム剤)を使用し、病原菌密度を下げるようにする。その際、土壌消毒剤の使用方法を確実に守って使用すること。特に、カーバムナトリウム剤は、使用する際の土壌水分や確実なガス抜きの実施など使用方法を誤ると効果が出ないばかりか薬害が起こる可能性もあるので十分な注意が必要である。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日
シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日 -
 農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日
農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日 -
 【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日
【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日 -
 イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日
イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -
 農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日
農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -
 (429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日
(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -
 米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日
米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -
 「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日
「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -
 JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日
JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -
 素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日
素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -
 JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日
JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -
 真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日
真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -
 3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日
3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -
 自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日
自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -
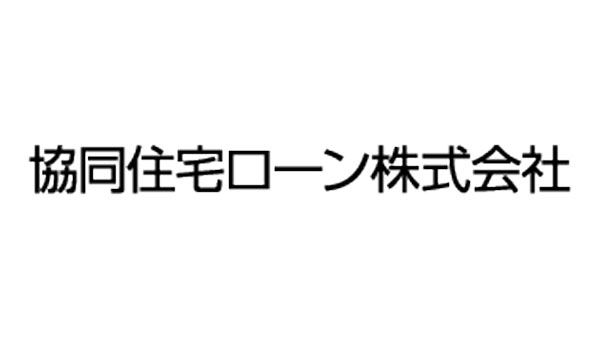 【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日
【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -
 大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日
大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -
 【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日
【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -
 鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日
鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -
 全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日
全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日

































































