農薬:防除学習帖
みどり戦略に対応した防除戦略(2)【防除学習帖】第208回2023年7月15日
令和3年5月に公表され、農業界に一定の衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にKPIをクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上で、みどりの食料システム法のKPIをクリアできる方法がないかを探ろうとしている。
前回、みどりの食料システム法における化学農薬使用量減の考え方、リスク換算値の算出方法を紹介した。具体的な内容に入る前に断りを入れておきたいのが、前回紹介したリスク換算値は、有効成分ごとの2019農薬年度出荷量をもとに算出したので単純な計算ができたが、実際の防除例をもとに削減方法を検証しようとするには、そこに使用されている農薬の有効成分含量や散布回数を計算に入れなければならないことである。リスク換算値は、有効成分ごとに算出するルールなので、当然ながら、使用された農薬製剤ごとに、含まれる有効成分の数と含量%をあらかじめ確認しておく必要がある。
ただ、このリスク換算値は2019農薬年度の出荷量が多かった農薬を減らす対応を取らざるを得ない可能性が高く、その際に他の農薬に置き換わる案を提示せざるを得ない場合もありうる。そういった情報を公にすることは、公平性が求められ得る本誌の立場からすると不適切であると考える。このため、有効成分名については記号を使って実名を伏せ、より効果的かつ効率的なみどり戦略対策を作りあげる際の考え方を中心に整理していきたい。若干具体性にかけてイメージが付きづらい点があるかもしれないが、あらかじめご容赦願いたい。
また、みどり戦略に対応した防除戦略は、当然ながら作物別に考えていく必要があるので、水稲、畑作、施設園芸、露地園芸、果樹といった分野ごとに、それぞれで代表的な作物を題材に整理を進めていきたい。まずは、防除回数が少なく、空中散布剤など本田期に散布する農薬を除き、1作あたり1回の散布で防除が終了する有効成分が多いという特色のある水稲栽培を題材に検討を進めていこうと思う。
1.水稲栽培におけるみどり戦略対策
水稲栽培では、栽培ステージで使用する農薬や使用方法が異なる。このため、みどり戦略対策を検討する際には、まず栽培ステージごとに戦略を考え、最後に1作期を通じての対策を検討することとしたい。
栽培ステージは、種子消毒、播種・育苗、移植、生育期、収穫期の5つに分けて検討する。
2.種子消毒におけるリスク換算と対策の方向
(1)種子消毒の実施場所
水稲の病害虫には種子伝染性の病害虫が多くあり、いもち病のように苗での発生が1作期の発生量を左右させるような病害もある。このため、県推奨品種など種子更新を義務化している品種などでは特に徹底した種子消毒が実行されている。
この種子消毒の方法には、種子供給施設での大量処理、JA等の育苗センターにおける種子消毒、直播用種子への種子処理、農家の庭先での種子消毒などまちまちである。最近は購入種子や購入苗が増えたので、大半は種子供給施設かJAの育苗センターでの処理となるであろう。
(2)種子消毒のタイミング
種子消毒は、種まきのタイミングに合わせて処理される。種もみを播種する前には、種もみに十分に水を吸収させる段階である「浸種」、芽を出させる段階である「催芽」といった作業がある。この作業の前後で種子消毒剤を処理して種もみの中に潜む病原菌やシンガレセンチュウを防除する。種子消毒剤の処理タイミングには、浸種前(秋処理含む)、浸種時、催芽前、催芽時、播種時があり、病害虫の特性などに合わせて最も効果を発揮できるように使用時期が定められている。
(3)処理方法
大きく分けて、乾燥種子に対して、薬液や薬剤の粉をまぶす方法(種子粉衣やスラリー処理と呼ばれる)や薬剤の希釈液を作成して高濃度短時間(処理例:20倍液10分間処理)か低濃度長時間(処理例:200倍液24時間処理)といった具合に種子を浸漬して処理する方法、薬液を処理機械で吹き付けて処理する方法が主なものである。
みどり戦略対応でリスク換算値を計算する場合、それぞれの処理方法で農薬の有効成分がどの位の量が種子に処理されたかを計算するので、薬剤ごとの有効成分含量と希釈倍数と処理液量、または種もみ重量あたりの処理薬量が必要になる。
(4)種子消毒剤の処理方法別リスク換算値の計算
①種子粉衣の場合
この方法は最も処理量が計算しやすい方法である。処理の仕方は、あらかじめ表面に水分を含ませておいた種籾に乾燥種子重量の0.5%相当量の薬剤をまぶして、種子の表面に薬剤を付着させ、風乾して固着させるものである。平均的に育苗箱1枚あたり乾燥籾180g、10aあたり20枚の箱を田植えするので、10aに田植えするのに必要な種籾の量は180g×20枚=3,600g=3.6kgである。
この種籾の0.5%量なので、使用する薬剤の有効成分%が20%だとすると、10aあたりの種子消毒剤有効成分量は、3,600g×0.5%×20%=3.6g(/10a)といった計算になる。
これにリスク係数を掛けることになるが、種子消毒剤はリスクが中程度から小さいものが多いので、この試算では中間の0.316を採用して、リスク換算量を算出する。
本来なら経営面積全体でのリスク換算量を算出するところだが、みどり戦略KPIでは割合での削減が目標なので、10aあたりのリスク換算量で比較することとする。
②その他の処理方法の場合
粉衣以外の処理方法を同様に計算すると、一覧表のとおりとなる。
![みどり戦略に対応した防除戦略[2]](https://www.jacom.or.jp/nouyaku/images/0263b4290cc132a4438d15541f921ac7.jpg)
(5)対策の方向
種子消毒で化学農薬の使用量を減らすためには、次のような戦略があるが、これらは種子消毒分野に限ってのことである。みどり戦略ではリスク換算量の総量なので、実際にどの分野のどの農薬を減らして、どの農薬を温存するかといったことは、全ての分野の数値を算出してからでないとわからない。
以下の対策は、「この分野で減らそうと思えばこのような方法がある」程度のとらえ方に留めておいてほしい。
(対策1)有効成分使用量(リスク換算量)の小さい処理方法へ変更する
試算すると、高濃度短時間処理(20倍液10分浸漬)が最も種子消毒剤の使用量(リスク換算量)が多く、他の処理法より約10倍以上の開きがある。現在、高濃度短時間処理を行っているのであれば、処理方法を他の方法に変更するだけで大きな削減効果が得られる。例えば、高濃度短時間処理のリスク換算量は22.8なので、リスク換算量2.3の低濃度長時間処理に変更するだけで9割の削減になる。ただし、既に粉衣や吹付処理している場合は、この方法は使えないので、他の分野での対策を考える必要がある。
(対策2)化学農薬から生物農薬もしくは温湯消毒へ変更する
種子消毒の方法を、化学農薬の利用から生物農薬や温湯消毒に変更すれば、リスク換算量は0(ゼロ)にできる。ただし、生物農薬や温湯消毒の場合、防除効果が不十分な場合があるので、その病害発生のリスクを考慮する必要がある。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日
【注意報】水稲の斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 山口県2025年7月8日 -
 なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日
なぜ米がないのか? なぜ誰も怒らないのか? 令和の米騒動を考える2025年7月8日 -
 2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日
2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【立憲民主党】「食農支払」で農地と農業者を守る 野田佳彦代表2025年7月8日 -
 2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日
2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【自由民主党】別枠予算で農業を成長産業に 宮下一郎総合農林政策調査会長2025年7月8日 -
 2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日
2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【日本共産党】価格保障・所得補償で家族農業守る 田村貴昭衆議院議員2025年7月8日 -
 2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日
2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」 【れいわ新選組】農業予算倍増で所得補償・備蓄増を やはた愛議員2025年7月8日 -
 【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日
【第46回農協人文化賞】集落と農地 地域の要 営農事業部門・広島市農協組合長、広島県農協中央会会長 吉川清二氏2025年7月8日 -
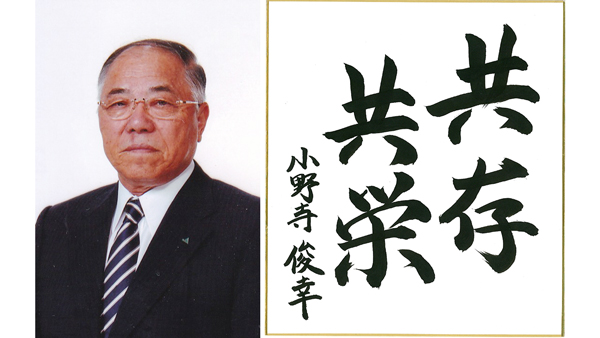 【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日
【第46回農協人文化賞】若者を育てる農協に 営農事業部門・北海道農協中央会前会長、常呂町農協前会長 小野寺俊幸氏2025年7月8日 -
 小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日
小泉農相 随契米放出に「政策効果」 市場落ち着けば備蓄水準戻す2025年7月8日 -
 トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日
トランプ政権の移民摘発 収穫できず腐る野菜「農家に大きな打撃」2025年7月8日 -
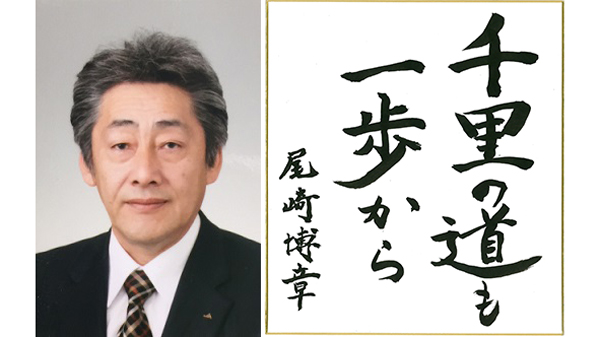 【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日
【第46回農協人文化賞】常に農協、農家のため 営農事業部門・全農鳥取県本部上席主管 尾崎博章氏2025年7月8日 -
 150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日
150年間受渡し不履行がなかった堂島米市場【熊野孝文・米マーケット情報】2025年7月8日 -
 2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日
2025参院選・各党の農政公約まとめ2025年7月8日 -
 米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日
米価 6週連続低下 3600円台に2025年7月8日 -
 【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日
【JA人事】JA秋田しんせい(秋田県)佐藤茂良組合長を再任(6月27日)2025年7月8日 -
 【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日
【JA人事】JA北九(福岡県) 新組合長に織田孝文氏(6月27日)2025年7月8日 -
 【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日
【JA人事】JAかながわ西湘(神奈川県)天野信一組合長を再任(6月26日)2025年7月8日 -
 【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日
【JA人事】JAえひめ中央(愛媛県)新理事長に武市佳久氏(6月24日)2025年7月8日 -
 宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日
宇都宮市に刈払機を寄贈 みずほの自然の森公園へ感謝と地域貢献の一環 JA全農とちぎ2025年7月8日 -
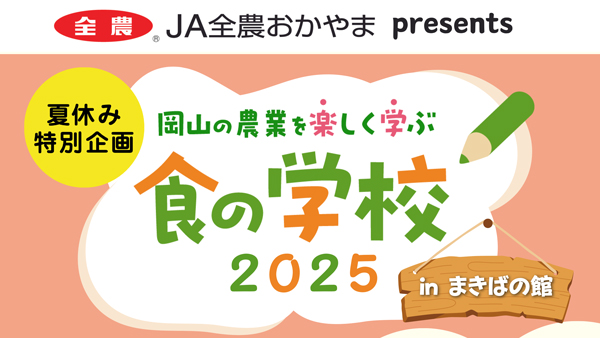 岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日
岡山の農業を楽しく学ぶ 夏休み特別企画「食の学校2025」 JA全農おかやま2025年7月8日
























































