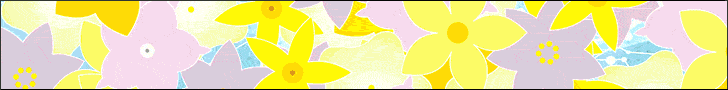農薬:防除学習帖
みどり戦略に対応した防除戦略(16)トマトの生育期の農薬【防除学習帖】 第222回2023年10月28日
令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にKPIをクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上で、みどりの食料システム法のKPIをクリアできる方法がないかを探ろうとしている。
現在、農薬の使用量も多く、出荷量も多いトマトを題材にして、どんなリスク換算量の低減方策があるのか探っており、まずは、トマトの防除タイミング(場面)ごとにリスク換算量を減らす方策にどんなものがあるか検証している。検証する防除タイミングは、①苗の本圃への植付前、②育苗期後半~植付時、③生育期の3つであり、今回から③の生育期に使用する農薬について検証する。
1.生育期の農薬使用場面と10aあたりリスク換算量
トマトの生育期には多種多様な病害虫が発生する。このため、トマトの品質と収量を考えれば、様々な農薬が使用され、恐らく全く同じ農薬が同じように使用されているのは稀だろう。
なぜなら、トマトの野菜の場合、果樹のような共通防除暦で同じ防除が行われることはなく、それぞれの圃場で、生産者の判断で使用する農薬・方法が決定され、使用されるからだ。恐らく、生産者の数だけ防除体系があるとみても良いだろう。
防除効果を優先することを考えれば、この時期の農薬を減らすことは直接的に収量・品質の低下に結びつくのであまり減らすことは考えない方が良いかもしれない。
2.みどりの食料システム法対応の検討
前述のとおり、この処理時期の薬剤については、リスク換算量はあまり意識せずに、防除効果を優先すべき時期だ。
作期全体を通してのリスク換算量の低減に与える影響は少ないかもしれないが、あえて実施しようとするならば、以下のとおりの対策が考えられる。
(1) 薬剤の1回当たりの処理量を減らす
これは一番わかりやすい方法である。登録の希釈倍数が1000倍~2000倍であれば、希釈液が薄くて含まれる農薬の製剤量が少ない2000倍での散布を採用する。登録の薬量が株元20g~30gするとリスク換算量を1/2に減らせる処理量が1~2g/株などと幅がある場合は、少ない方の処理量を選択すれば、リスク換算量を減らせる。
例えば、登録内容が1~2g/株となっている農薬の場合、株あたり2g処理のリスク換算量は、これを株あたり1g処理に変更するだけで50%削減となる。
ただ、削減率の上では大きいが、トマト作期全体のリスク換算量に与える影響は少ないので、残効性と効果の安定性を考えれば、処理量は登録の範囲で多い方がいいだろう。
(2)リスク換算量の少ない薬剤に変更する
リスク換算量を比較して、単純にリスク換算量が少ない薬剤を選択すればよい。前述のように、この使用時期はトマト作期全体のリスク換算量に与える影響は小さいので、わずかなリスク換算量の削減を目的に、あえて薬剤を変更する必要はないだろう。
(3)適用病害虫の幅が広い薬剤を使用する
トマトの生育期には、いくつもの病害虫が同時発生する場合が多い。
例えば、生育期に病害が3つ発生したとすると、その防除には単純に異なる有効成分の3つの農薬が必要になる。この時もし、1つの有効成分で3つの病害を防除できる有効成分があったとすると、3病害を1成分で同時防除すれば、3つの農薬で防除していた時に比べ、単純にリスク換算量は3分の1になる。
ただし、これは有効成分の含有%やリスク係数が同じと仮定した場合の話で、実際には有効成分の含有%やリスク係数は農薬ごとに異なるので、リスク換算量の削減量は異なってくるだろうが、使用する成分数を減らすことができればリスク換算量を減らすことができるのは間違いない。
(4)できるだけ残効期間の長い薬剤を使用する
トマトは作期が長く、1つの病害虫の発生期間も長いため、一定の間隔で何回も防除することになる。
この際、残効が長い農薬を使用すれば散布間隔を長くすることができ、散布回数を減らすことができる。散布回数を減らすことができれば、それに応じて農薬のリスク換算量を減らすことができることになる。
(5)生物農薬などリスク換算値ゼロの農薬を使用する
トマトには使用できる生物農薬、天敵資材が多数ある。これらを有効活用することで、化学農薬の使用量(リスク換算量)を減らすことができる。
(6)散布以外の方法に変更する
トマト防除では農薬を希釈して散布するのが一般的だが、それを常温煙霧やくん煙など有効成分投下量の少ない散布方法に変更することで農薬のリスク換算量を減らせる可能性がある。
以上がトマト生育期防除におけるリスク換算量を減らす方策だが、これらのリスク換算量を減らす効果がどの程度あるか、対象病害虫や使用方法に例をとって、次回以降、方策別に検証を進めてみようと思う。
重要な記事
最新の記事
-
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日 -
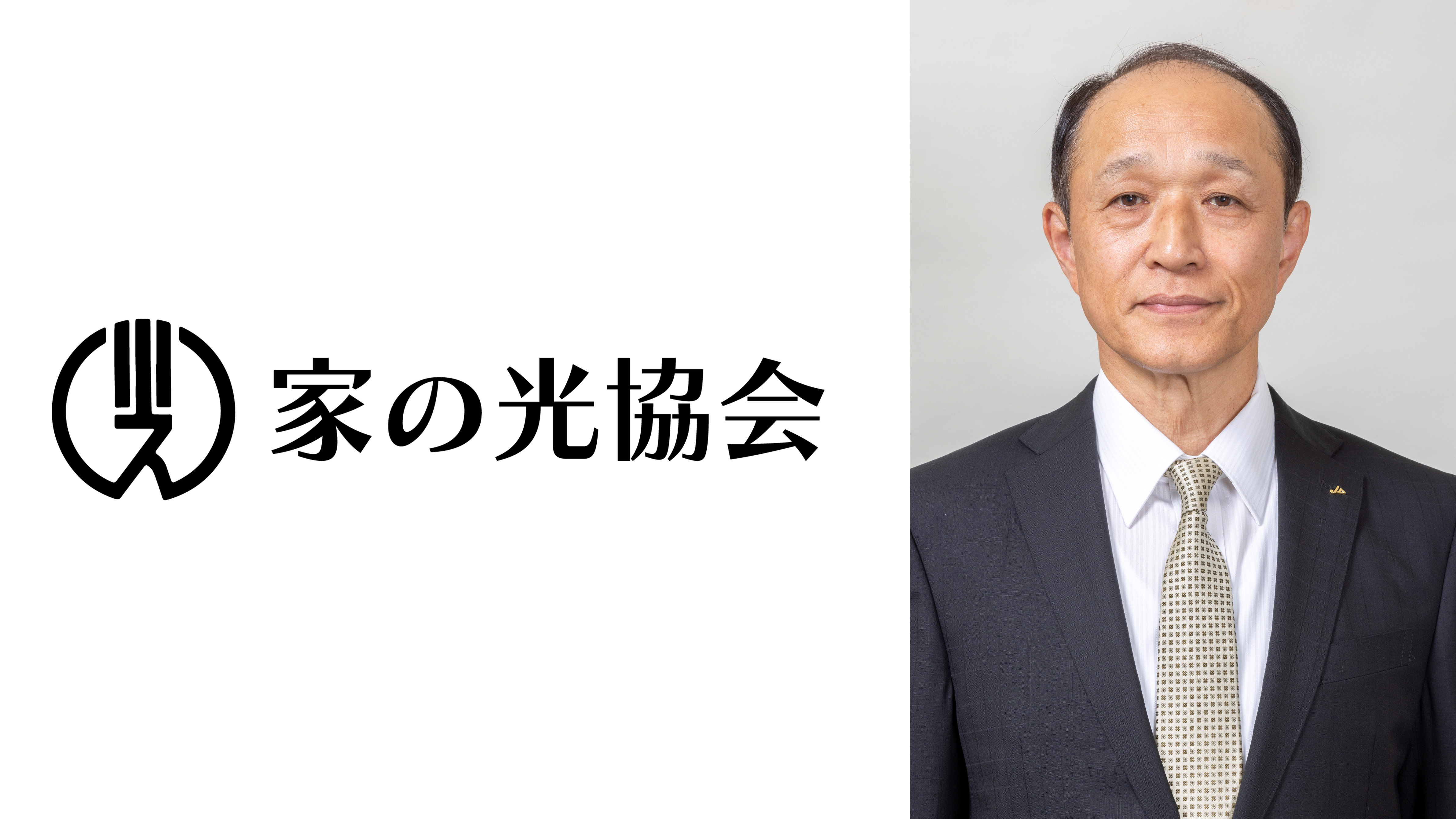 【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日 -
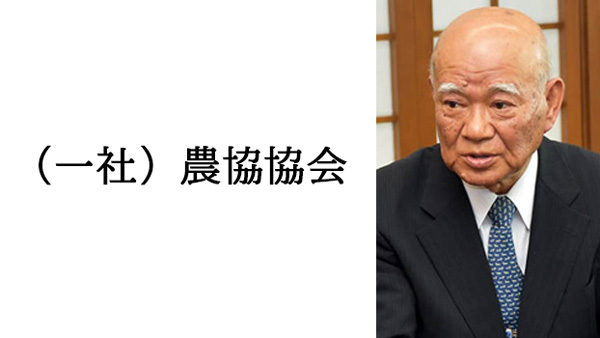 【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日 -
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日