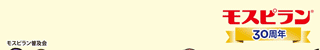農薬:防除学習帖
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(9)【防除学習帖】 第248回2024年5月4日
令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上でKPIをクリアできる方法を探っているが、そのことを実現するのに必要なツールなり技術を確立するには、やはりIPM防除の有効活用が重要だ。そこで、防除学習帖では、IPM防除資材・技術をどのように活用すれば防除効果を落とさずに化学農薬のリスク換算量を減らすことができるのか探っている。
IPM防除は、化学農薬による化学的防除に加え、化学的防除以外の防除法である①生物的防除や②物理的防除、③耕種的防除を効率よく組み合わせて防除するものである。化学的防除に関しては、以前本項において検証・紹介したので、現在、次の段階として化学的防除以外の防除法について、その技術的な概要と導入にあたっての留意点を紹介している。
前回から物理的防除について紹介しており、今回は、熱を利用した防除法の続きをご紹介する。
1. 熱を利用した防除法の技術的概要(おさらい)
物理的防除法の中でも熱を利用した防除法は、過去から多く利用されてきた歴史のあるものである。この方法は、何らかの熱源によって土壌や施設内を病害虫雑草が死滅する温度にまで上昇させて、病害虫雑草を防除する方法で、現在も利用されている防除法には、蒸気消毒法、熱水消毒法、温湯消毒法、太陽熱消毒法、土壌還元消毒法といったものがある。
これらの防除法の成否のカギは、土壌還元消毒法を除くと、防除対象とする病害虫雑草の死滅温度、つまり病害虫であれば60℃10分以上、雑草種子であれば湿度が高い状態で70℃30分以上を目安として、この温度に達するまで土壌や施設内の温度を高め、一定時間その温度を保持することである。
この時問題となるのは、病害虫雑草が存在する土壌内の深度である。一般的な作土層は15cm程度といわれるが、病害虫雑草によってはその深度を越えて、例えば土壌表面から30cmの深さにも存在することがあるので、特に根が深い作物を作付けする場合は、深耕ロータリーで消毒を行う前によく耕耘しておく必要がある。
要は、作土層内全体(土壌表面~作土層最深部)が病害虫雑草の死滅温度に達しやすくなるようにしておく必要がある。温度を上昇させる方法は消毒法によって異なるが、温度が上昇しきれていない部分は、病害虫雑草を取りこぼすことになり、そういった場合には、わずかに生き残った病害虫雑草が回りの土壌にライバルがいない中、寡占的に増殖する場合があるので、取りこぼしが無いよう、作土層全体が熱を持てるように仕向ける必要がある。
また、線虫などは消毒できた層より下層にいたものが、地下水の動きとともに上昇する場合があることを理解しておく必要がある。
2. 熱を利用した主な物理的防除法と活用上の留意点
(1)太陽熱消毒
十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりとあて、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。
病原菌の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場がカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60℃に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。
(2)土壌還元消毒法
この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。最近では、千葉県などで、フスマや米ぬかの代わりにエタノールを使用する方法が考案され活用されている。これにより、土壌に混入された有機物をエサにして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、害虫や病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。ただし、還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間をおく必要がある。また、近隣に住居があるような圃場では臭いの発生に注意が必要である。
(3)ハウス内蒸しこみ
この方法も日照がしっかりとある地域の施設栽培向けの方法である。施設トマトやキュウリなどに発生するコナジラミ類やアザミウマ類、ハモグリバエ類は作物を食害・吸汁する他、コナジラミ類やアザミウマ類については各種ウイルス病を媒介し、しばしば重篤な被害を及ぼす。
これらは一旦発生すると害虫やウイルス病の伝染環を完全に絶つのが難しくなるので、この伝染環を断つために、施設栽培の終了した後に、生きたままの害虫を施設外に逃がさないように留意しながら被害残渣を施設内に横倒しにし、施設内蒸し込み処理などを実施すると害虫を死滅させることができる。また、作物残渣内の病原ウイルスも熱によって不活化させることができる。
蒸しこみ作業は次のような手順で実施する。①栽培終了後に栽培作物の株元を切断するか又は抜き取った後に土俵面に倒して、②ハウスを密閉し、施設内内温度が40℃を超える期間が10日以上となるようまで密閉を継続するだけである。なお、施設内には、高温により障害の出る機材等がある場合は、施設外へ持ち出すか、機材を遮光を行うなどの処置を行って保護すると良い。
より蒸し込みの効果を高めるためには、株元を切断するか又は抜き取った株を畝上に寝かせて並べ、その上に透明ビニールをべた掛けすると、茎葉部の温度をより上昇させることができ、効果も安定する。この場合は、天窓を開放して施設内温度を下げることができるので、施設内に移動できない熱に弱い設備がある場合は、透明ビニルのべた掛けを検討すると良い。
なお、蒸し込み終了後は、念のため残渣を施設外から全て排出し、許されている場合は焼却などで適切に処理するとより伝染環を断ち切ることができる。
重要な記事
最新の記事
-
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日
和牛農家と海外バイヤーをつなぐオンラインプラットフォーム「WAGYU MARKET」提供開始2026年1月30日 -
 酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日
酪農業の地域特有の課題解決へ 酪農家との情報交換会「第5回MDA MEETING」地域別開催 明治2026年1月30日