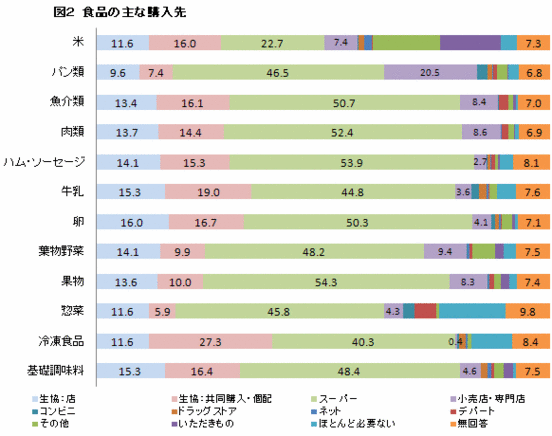【2012年度全国生協組合員意識調査報告書から】 生協組合員・食品の購入先はスーパーが一番2013年2月22日
・組合員の3割は「1万円未満利用」
・スーパーより生協利用が多いのは「米」だけ
・「安全性」や「産地」より「便利さ」を優先
・事業の創造的挑戦で都市と農村の連携を
1980年代、日本の地域生協は食の安全性や産直事業によって、オピニオンリーダー的存在として日本の小売業とくに食品流通を牽引していたといえる。あれから30年近くが経過し、地域生協は2000万人近い組合員を擁し、共済や福祉事業を除いた事業高は2兆6000億円(2011年度)にのぼる一大勢力となった。しかし、生協は80年代当時と比べて「様変わり」したのではないかと考える人は少なくない。それは事業の規模の問題ではなく、組合員の意識としてだ。昨年11月末に日本生協連が公表した「2012年度全国組合員意識調査報告書」をみるとその感をより深くする。そこで、この「調査報告書」から、生協事業への組合員の意識の変化をみてみることにした。
「近さ」と「価格」で選ぶ“現実”
◆組合員の3割は「1万円未満利用」
 日本生協連は「全国生協組合員意識調査」を3年ごとに実施しており、2012年度は、12年6月に実施され、30生協4080名(6000名に調査票配布、回収率68.0%)の回答を得て「報告書」としてまとまられた。
日本生協連は「全国生協組合員意識調査」を3年ごとに実施しており、2012年度は、12年6月に実施され、30生協4080名(6000名に調査票配布、回収率68.0%)の回答を得て「報告書」としてまとまられた。
設問は「くらしの変化と社会や経済についての考え方」「東日本大震災後のくらしの変化」「生協の活動について」「生協の共催について」「生協の利用と、これから期待すること」そして「回答者自身について」の36問だが、本紙が注目したのは、そのなかの食品を中心とする生協事業の利用額や主な食品の購入先に占める生協の割合などにに関する項目だ。
図1は、「1か月の生協利用額」を06年から12年の3回の調査結果をまとめたものだが、「利用していない」が6.9%から12.7%へ、「1万円未満」が21.5%から29.0%へ増加しているが、それ以外の金額は減少していることがわかる。
日本生協連によれば、地域生協の事業高は02年度の2兆4773億円から11年度の2兆6840億円(共済、福祉事業含む)へと増加してきているが、それは組合員数を増やすことで実現しきた結果だといえる。なぜかといえば「1人当たり利用高」は03年の1万4170円から11年の1万1546円へと2割近く減少しているからだ。
つまり、いまや生協組合員であっても「生協は食品スーパーやコンビニと同じ『選択肢一つ』となっている」といえる。しかも、長年にわたって恒久的な赤字経営が続いている店舗事業では「1人当たり利用点数、利用単価は前年を超えているが、利用人数が前年割れを続けて、供給高は前年割れとなった」(12年6月の日本生協連第62回通常総会議案)と総括しているように、組合員の増加は店舗事業ではなく個配事業に偏っている。
さらに、店舗における生鮮分野(農産・水産・畜産・惣菜の4部門)の供給構成比を「他企業と比較すると、生協平均37.7%に対してSM企業43.9?47.7%、とりわけ成長部門である惣菜の構成比に大きな差が見られ」るとし、品揃えの改善と店舗内技術の向上で「生鮮分野の営業力強化を図り、利用人数の向上に向けた魅力的な店づくりを進めていくことが課題」だと総括している(同上)。
(写真)
2013年2月7日にリニューアルしたコープ熊谷店(熊谷市)(さいたまコープHPより)
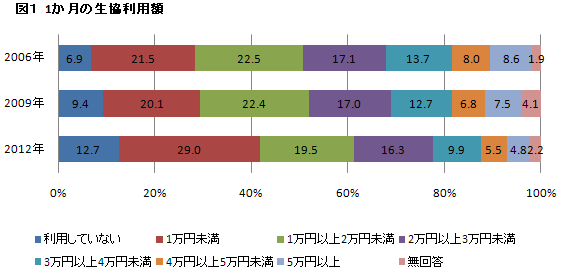
◆スーパーより生協利用が多いのは「米」だけ
「調査報告書」で具体的に主要食品の品目別の購入先をみたのが図2だ。これをみるとスーパーより生協(店舗+共同購入・個配)が上回っているのは「米」(27.6%対22.7%)だけだ。06年にはそれでも生協がスーパーより上回るのが5品目あったが、09年には「米」と「冷凍食品」、12年は「米」だけになってしまった。
表1は、09年の調査と比較した生協とスーパーの購入先割合の変化だが、生協では「惣菜」が0.1%増えている以外は、すべての品目でマイナスとなっている。12年調査でスーパーより購入先として多く選択されている「米」でも▲2.4%と減少し、スーパーは3.6%増えていることにも注目しておく必要があるといえる。かつて「安全でおいしい牛乳を」というのが地域生協へ結集する合言葉の時代もあったが、生協組合員の45%はスーパーで購入しており、時代の移り変わりを感じさせる。
※表はクリックすると大きくなります。
◆「安全性」や「産地」より「便利さ」を優先
その購入先を選択した理由を牛乳でみると「近い」が最も多く32.3%、次いで「価格が安い」27.9%と続き、生協組合員らしい選択肢だといえる「安全性が高い」は19.2%、「産地が明確」は7.9%となっている。
「葉物野菜」では「新鮮」が33.0%ともっとも多くなっているが、次いで「近い」30.5%、「価格が安い」26.6%となっており、「産地が明確」は16.4%、「安全性が高い」14.6%となっている。
つまりどの品目をみても「安全性」「産地が明確」よりも「近い」(買い物に便利)と「価格の安さ」が生協組合員が購入先を決める要因となっていることが分かる。とくに「店舗のみ利用者」にこの傾向が強い。「個配」や「共同購入」利用者」の場合は、全体の平均よりは「安全性が高い」との回答が増える傾向にあるが、当然のことだともいえるが「配達が便利」という回答が多いのも特徴だ。
そして今後の「生協の新商品開発において優先すべきと思うこと」では、「健康やカロリーに配慮した食品や商品」(06年45.7%から12年48.7%へ)「便利さに着目した商品」(同27.8%→40.6%)「これまで以上に低価格な商品」(同23.4%→35.3%)「外国産を含めて品質など優れた原料を活用した商品」(同12.1%→19.6%)となっている。そして「もっと環境に配慮した商品」は同27.5%から14.0%へと減少していることも象徴的なことだといえるかもしれない。
◆事業の創造的挑戦で都市と農村の連携を
こうした調査結果を踏まえて、「第29回全国産直研究交流会」(2月8日開催、関連記事参照)で基調講演した京都大学の若林靖永教授は「現在の組合員構成のボリュームゾーンに対応するためには、『価格』『品質』『品揃え』『情報提供』を強めるべきで、『産地の明確化』等は購入先選択において相対的重要度は低い」「現在のやり方では少数派、2番手としての生協というポジションになり、競争劣位に陥る」。「かといって、スーパーと直接競合する方向は、生協利用者を失うことになりかねない(すでにオーガニック志向等の消費者は他のとがった流通業者を利用している)」と指摘。
そのうえで、生協の産直は「なぜ農業を重んじるのか、哲学、使命感、情熱が問われている」とし「目的・目標はなにかを明確に生協経営組織・組合員組織で共有・確認」し「生協産直の焦点・中心を明確にして、事業の創造的挑戦をすすめる」ことだと述べ、そのうえで「農村コミュニティと都市コミュニティとの連携・協同という目的・目標の決定的重要性を提起したい」と結んだ。
若林教授の指摘は非常に示唆に富むものだといえるが、この3月には280万人強の「生協みらい」と180万人の「ユーコープ」が誕生するという新たな展開をむかえるなかで、生協がかつてのように消費者のオピニオンリーダーとしての輝きを取り戻すことできるのか。取り戻してくれることに「期待を込めて」見守りたいと思う。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日
シンとんぼ(138)-改正食料・農業・農村基本法(24)-2025年4月19日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(55)【防除学習帖】第294回2025年4月19日 -
 農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日
農薬の正しい使い方(28)【今さら聞けない営農情報】第294回2025年4月19日 -
 若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日
若者たちのスタートアップ農園 "The Circle(ザ・サークル)"【イタリア通信】2025年4月19日 -
 【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日
【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -
 3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日
3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -
 地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日
地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -
 主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日
主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -
 米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日
米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -
 「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日
「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -
 (431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日
(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -
 JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日
JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -
 商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日
商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -
 JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日
JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -
 地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日
地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -
 冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日
冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -
 農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日
農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -
 農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日
農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -
 日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日
日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -
 森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日
森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日