食品の機能性表示制度で意見書 生活クラブ生協連2014年10月29日
生活クラブ生協連は、「食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)」について、パブリックコメントを提出した。
このパブリックコメントで生活クラブ生協連は、
△今回の制度設計のありかたそのものものに、企業の便宜のみを優先する、根本的な矛盾があると考え、「サプリメント」に関しての消費者の信頼性を高め、また健康被害を防止する観点から、まずサプリメントそのものを、食品と切り離して規制する法整備を行うべき。
△「企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる」とする現在の制度設計では、国の責任があまりにも不明確。国は表示される機能性食品に関して、消費者庁への届け出だけに留めず、科学的根拠に関して特定保健用食品に準じた審査と監督を行う責任がある。
△機能性成分の製造原料の内容や抽出(製造)方法、機能性成分の製造国や製造メーカー、および機能性表示食品中の機能性成分の含有割合(重量等)等について消費者への情報開示を企業に義務付けする必要がある。
と述べている。
パブリックコメントの全文は以下の通り。
【食品表示基準2条】
今回検討されている機能性表示食品には、市場で、いわゆる「サプリメント」と称して販売されるものが含まれています。「サプリメント」の多くは、錠剤もしくはカプセル入りの形状をしており、これらの薬品様の形状のものは従来、薬事法が管轄するものでした。「新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)関係資料」(平成26年8月消費者庁食品表示課)の「はじめに」では、食品の3つの機能について記載されていますが、食品とは本来2次機能(味覚・感覚面での働き)を持つものであり、「サプリメント」は、1次機能(栄養機能)と3次機能(体調調節作用)しか保有していません。このような「サプリメント」を、法の上で食品として位置づけ続け、表示に関する法整備のみで機能性を認めていくという、今回の制度設計のありかたそのものものに、企業の便宜のみを優先する、根本的な矛盾があると考えます。「サプリメント」に関しての消費者の信頼性を高め、また健康被害を防止する観点から、まずサプリメントそのものを、食品と切り離して規制する法整備を行うべきです。
【食品表示基準3条の2 および第九条】
「食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)関係資料」(平成26年8月消費者庁食品表示課)によれば、新制度の設計は「消費者の誤解を招かない自主的かつ合理的な商品選択に資する制度」とされています。また「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会報告書」(平成26年7月30日)では、可 能な機能性表示の範囲として、「疾病の治療効果又は予防効果を暗示する表現や「肉体改造」等の健康の維持・増進の範囲を超えた、意図的な健康の増強を標ぼ うするものと認められる表現は、医薬品との薬事法の対象となることに留意すべきである」とされています。
しかしながら、同報告書の「対象者」の項には、「生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は、境界線上の人を対象とし、疾病に既に罹患している人(医薬品に より治療されるべき人)に対して、機能性を訴求する製品開発、販売促進等は行わないことが適当である。」とされていいます。
健康診断等でいわゆる「生活習慣病」の境界線上にあると指摘された消費者の多くは、現時点であっても病気に進行してしまう前の予防効果を期待していわゆる「健康食品」等を購入しています。今回、機能性表示食品は、「身体の特定の部位に言及した表現を行うことも可能とすることが適当である。」(食品の新たな 機能性表示制度に関する検討会報告書)とされています。機能性表示食品の対象者に「生活習慣病等の境界線上の人」を選定するのであれば、当然ながら、それらの人は、疾病予防効果としての機能性をより強く期待して、その機能性表示食品を購入するものと思われます。加えて、表示においては、医薬品のように「疾病に罹患している者の医師への相談」や「体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師へ相談すべき」旨の記載が想定されています。使用に関して医師の 関与があらかじめ想定されているにもかかわらず、機能性表示食品を「企業等の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できる」とする現在の制度設計では、国の責任があまりにも不明確です。国は表示される機能性食品に関して、消費者庁への届け出だけに留めず、科学的根拠に関して特定保健用食品に準じた審 査と監督を行う責任があると考えます。
【食品表示基準三条の2】
前述しましたように、機能性表示食品においては、「疾病に罹患している者の医師への相談」や「体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師へ相談すべき」旨が記載されることが想定されています。これは、機能性成分そのものについて、ある種の副作用や過剰摂取の症例も発生しうるものとして予測されている ものです。機能性表示食品の多くは、ある特定の機能性成分を濃縮や増量して添加する場合が多数を占めるものと思われます。消費者にとって、健康被害の防止を図ることは重要な課題です。機能性成分の製造原料の内容や抽出(製造)方法、機能性成分の製造国や製造メーカー、および機能性表示食品中の機能性成分の含有割合(重量等)等について消費者への情報開示を企業に義務付けする必要があります。
(関連記事)
・「加工食品に不安」8割 日本公庫が意識調査(2014.09.25)
・日本・カナダ 有機制度の同等性で合意(2014.09.24)
・表示義務 早急に拡大を加工食品の原料原産地(2014.08.28)
・消費者の権利に基礎置く表示基準を 生活クラブ(2014.08.20)
・食品表示、TPP妥結前に基準化を パルシステム(2014.08.18)
重要な記事
最新の記事
-
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
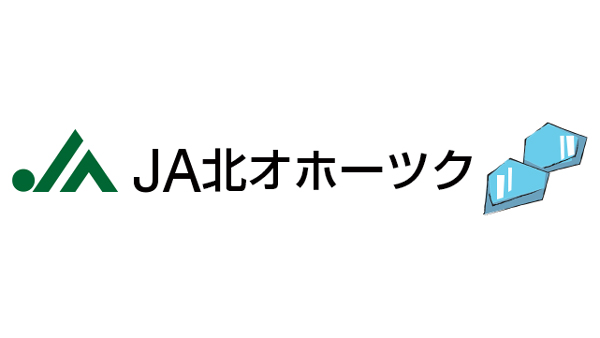 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -
 絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日
絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日




































































