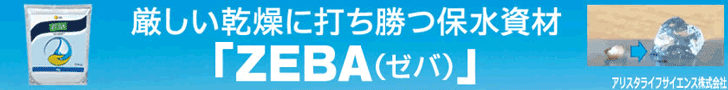流通:激変する食品スーパー
【第6回】「お客様の声」重視 思考停止の売り場は淘汰2015年9月2日
機動力を生かした運営店舗別管理
近年、勢いのある食品スーパーに採用されている運営スタイルの1つが「店舗別管理」だ。「店舗別管理」とは、各店舗のマネージャー等が仕入れと販売の権限を持ち、トータルな売場づくりを進めていくものだ。これと対極になる「本部管理」は、商品構成や仕入を本部に所属するバイヤーが中心となって行い、店舗側は陳列や補充、販売に専念することを言う。
◆GMSの売り場は面白みに欠ける
これまでの食品スーパーでは、主に店舗数の規模により管理体制を選択する考え方が浸透していた。例えば、5店舗程度であれば、本部機能を持たず、それぞれの店舗が独自で運営せざるを得ない。しかし、多店舗化を目指し、ある規模の店舗網が構築された段階で、仕入のスケールメリット(大量仕入れによる交渉条件の有利化)や標準化による作業効率向上を目的に、徐々に本部管理へと移行していく。そして、さらなる拡大と成長を実現させる体制を整え、「GMS(総合スーパー)」を代表とする全国展開のチェーンが生まれてきた。
しかしながら、いわば成熟したGMSは、どこに行っても画一的な売場で、面白みに欠けると指摘されることが多い。GMSのほとんどが地盤沈下を起こしており、例外なく苦戦を強いられているのもまた事実だ。
このように本部管理は、一元化による効率的な運営がしやすい一方で、買い物客のニーズや状況に応じた機動的な対応がしにくいデメリットがある。そこで多店舗化を実現しても、敢えて本部機能を限定し(場合によっては設置せず)、仕入れを店舗に任せて地域やお客様の要望に合わせた売場づくりを行っている企業が現れてきた。
◆完売をめざし工夫従業員もやる気
店舗別管理の売場の担当者はお客様とダイレクトに接し、仕入れた商品がどのように売れているかが即時に分かる。当然、本部でも販売データを見れば、動向は把握できるが、そこから「お客様の動き」「売れる理由」までを読み取るのは至難の業だ。また、購入の有無にかかわらず、「お客様の声」から次のビジネスチャンスを見出せる点も、店舗別管理ならではのメリットと言える。
お客様の声を反映した売場作りが、個性となり、競合他店との差別化の源泉につながっていることが、好調を支えている要因となっている。
さらに、管理体制の違いは販売する従業員の意欲にも影響する。店舗別管理の場合、自分が仕入れた商品を販売するので、その分販売に対する責任感がより強くなる傾向がある。仕入れた商品をどのように完売させるか、一生懸命考え、工夫しながら売場づくりを行っていく。その「執着心」の違いが売場に表れているような印象を持つ。本部管理の場合、全てではないもののバイヤーが決めた商品構成、送られてくる商品を販売する「だけ」と捉える従業員が存在するのも確かだ。「売れ残っても、自分の責任ではない」、「残ったら、値下げや廃棄で処理すればよい」などの考えに陥りやすく、売場づくりについての思考が停止し、お客様の変化に対応できていない店舗が増えているようだ。
【店舗別管理と本部管理のメリット比較】

◆臨機応変の運営へ人材育成が課題
最近では、本部管理に店舗別管理を一部埋め込んで運営する大手食品スーパーも現れた。なかには、新たな店舗フォーマット(※)を開発し、店舗に部分的な権限移譲を行い、独自の取り組みにつなげている例がある。同じチェーンであっても、お客様や地域の特性に応じて商品構成を変更し、店舗の魅力を高めると同時に、従業員のモチベーションを向上させる仕掛けとして活用している。
店舗別管理と言っても、それぞれが勝手に仕入れて販売するわけではない。一定の基準をベースに仲卸や他の市場に出向いている同僚からの情報を加味し、商品構成を組み立てている。また、店舗数の多い他の競合店では販売しにくいような生産量の少ない商品であっても、店舗別管理であれば積極的に仕入れて、売場の目玉に据えることも可能だ。課題は人材育成である。判断するための知識や販売状況に応じて臨機応変に売場を変更する創造力は個々の持つセンスに加えて、相応の教育が不可欠となる。これは一朝一夕には実現できず、ある程度の時間が必要となる。そのため、出店スピードに人材育成が追い付いていないと、売場運営が困難になり、競争力が低下するリスクを抱えている。
注目される店舗別管理ではあるが、選択する企業は限定的なものになるだろう。店舗別管理と本部管理、それぞれの管理方法に優劣があるわけではなく、様々な要素や外的要因を勘案しながら、使い分けや、組み合わせる動きは今後ますます加速していく。売場づくりに対して思考停止に陥った売場は淘汰され、そのテコ入れ策として店舗別管理による運営が有効である点は生産者にも知ってもらいたい。
※店舗フォーマット:企業が創り出す業態(営業の形態)のことで、ターゲットや目的に合わせた売り方の違いを指す。
重要な記事
最新の記事
-
 【年頭あいさつ 2026】岩田浩幸 クロップライフジャパン 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】岩田浩幸 クロップライフジャパン 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】片山忠 住友化学株式会社 常務執行役員 アグロ&ライフソリューション部門 統括2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】片山忠 住友化学株式会社 常務執行役員 アグロ&ライフソリューション部門 統括2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】佐藤祐二 日産化学株式会社 取締役 専務執行役員2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】佐藤祐二 日産化学株式会社 取締役 専務執行役員2026年1月3日 -
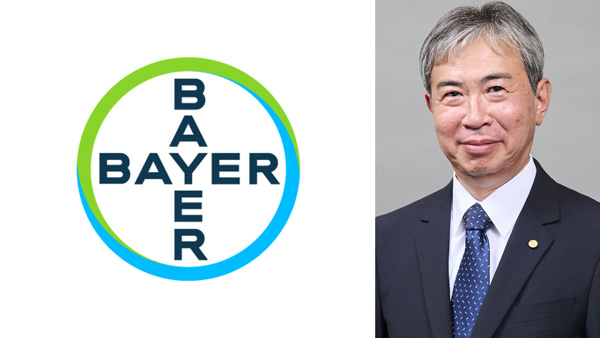 【年頭あいさつ 2026】大島美紀 バイエル クロップサイエンス株式会社 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】大島美紀 バイエル クロップサイエンス株式会社 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】栗原秀樹 全国農薬協同組合 理事長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】栗原秀樹 全国農薬協同組合 理事長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】佐藤雅俊 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】佐藤雅俊 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】雜賀慶二 東洋ライス株式会社 代表取締役2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】雜賀慶二 東洋ライス株式会社 代表取締役2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】松本和久 株式会社サタケ 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】松本和久 株式会社サタケ 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】冨安司郎 農業機械公正取引協議会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】冨安司郎 農業機械公正取引協議会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】増田長盛 一般社団法人日本農業機械工業会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】増田長盛 一般社団法人日本農業機械工業会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】菱沼義久 一般社団法人日本農業機械化協会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】菱沼義久 一般社団法人日本農業機械化協会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日 -
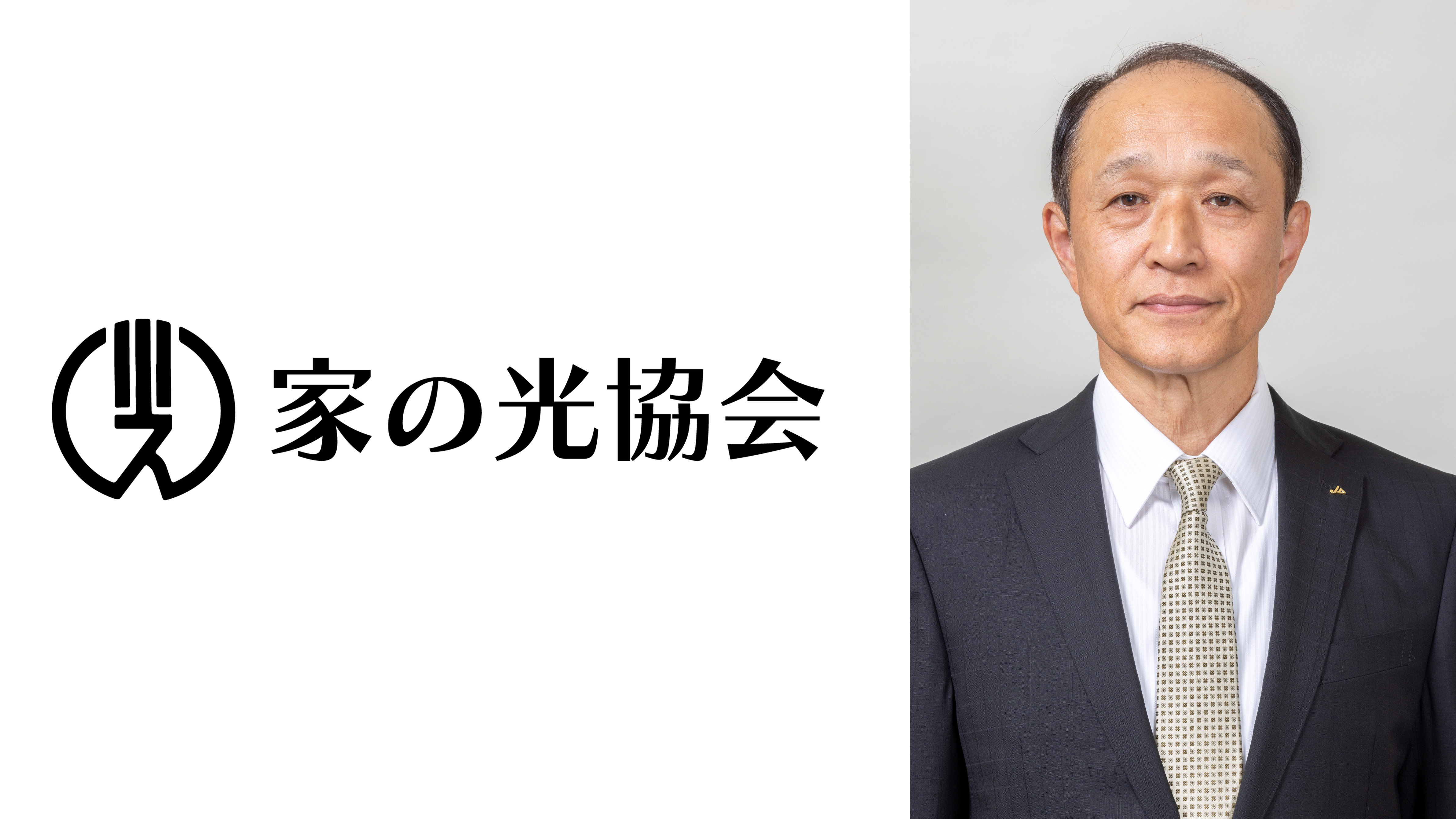 【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日 -
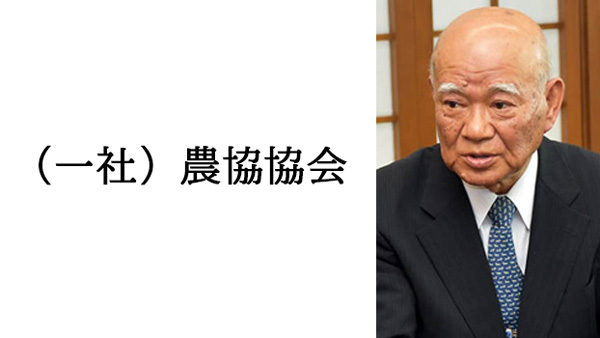 【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日 -
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日