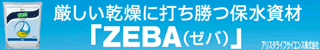日本農業労災学会創立 会長に三廻部氏2014年4月18日
日本農業労災学会が創立された。農作業事故を防ぐノウハウの普及と労災補償対策をすすめることを目的とするもので8日、東京都世田谷区の東京農大で創立総会を開き、会則、活動計画を決定。会長に労災予防研究所所長の三廻部眞己氏ほか役員を決めた。今年10月にシンポジウムと総会を開き、具体的な活動をスタートさせる。
事故防止ノウハウと
労災補償対策すすめる
 設立総会には発起人25人のほか、JA全国組織、農水省の関係者が出席。長年、農作業の安全対策について研究し、事故防止を呼び掛けてきた発起人代表の三廻部氏は、日本における農作業事故がいっこうに減らないことを挙げ、対策の遅れを指摘。農作業の安全対策は、「注意しろ」と呼び掛けるだけで、実際どうしたら防げるのか、現場に即して研究することの必要性を強調した。
設立総会には発起人25人のほか、JA全国組織、農水省の関係者が出席。長年、農作業の安全対策について研究し、事故防止を呼び掛けてきた発起人代表の三廻部氏は、日本における農作業事故がいっこうに減らないことを挙げ、対策の遅れを指摘。農作業の安全対策は、「注意しろ」と呼び掛けるだけで、実際どうしたら防げるのか、現場に即して研究することの必要性を強調した。
学会は今後、大会や研究会の開催のほか、新規就農者教育研修会、事故予防のノウハウを磨くセミナー、JAとの共催による事故予防のノウハウと労災補償の現地研修大会、地域農業の安全管理活動をリードする人材養成の講習会などを開催する。また、安全管理活動のモデル地区設定などの活動を計画している。
(写真)
設立総会のようす
◆「事故の連鎖断ち切って」萬歳会長
三廻部会長のほか、副会長に全国農業経営支援社会労務士ネットワークの入来院重宏会長、浅野社会保険労務士事務所長の浅野公司所長、東京農大の白石正彦名誉教授が決まった。
なお、設立総会にはJA全中の萬歳章会長が、「農作業事故発生、離農という悲惨な事故の連鎖を断ち切るため、農作業事故を着実に防ぎ、農業経営を持続的に発展させるため、今後はより具体的な事故防止のノウハウや労災補償対策が組織的に広く研究されることを期待しています」とのメッセージを寄せた。
「対策は具体的・実証的に」
労災予防研究所長・東京農大客員教授
三廻部眞己さん
◆人間愛に欠けている
 日本では農民の健康管理は進んでいるが、農作業事故の研究は遅れている。真剣に農作業事故ストップをめざした研究を行う学会がない。なぜ、農作業事故が防げないのか。農業以外の業界では、一環して事故が減少する傾向にあるのにである。これでは研究者の倫理観が不足しているといわざるをえない。人間愛に欠けているのではないか。
日本では農民の健康管理は進んでいるが、農作業事故の研究は遅れている。真剣に農作業事故ストップをめざした研究を行う学会がない。なぜ、農作業事故が防げないのか。農業以外の業界では、一環して事故が減少する傾向にあるのにである。これでは研究者の倫理観が不足しているといわざるをえない。人間愛に欠けているのではないか。
農家は、勤労者とくらべて所得格差が大きく、出稼ぎや兼業をせざるを得なかったが、そのため農業機械を購入し、一日でも早く農作業を終えようとした。また農機の借金を返済するためさらに出稼ぎに頼るようになった。これでは事故が起こるのは当然だ。JA中央会の助成で行った「ひやり、ハッと」のアンケートによると、農作業事故の37%が死亡に繋がっている。その実態を知ったとき、身震いする思いだった。
◆事故防止を営農指導の柱に
農作業事故を研究した本はほとんどなかった。このため研究が必要だということを農業試験場とも談判したが、反応は小さかった。何度も行くうちに、自分で論文を書けと言われて研究を始めたのだが、こうした実態は農政の貧困だといってもよいのではないかと思う。
というのも、事故は精神的に不安定な状況の時発生しやすいからだ。役所の人が多く参加した、ある学会で、農作業事故が減らないのは農政の欠点だとして発表したことがあるが、異質な発表として扱われた経験がある。
JAは、農作業事故防止を営農指導の柱にしなければならない。今の農村で、健康管理は100%といってよいほど充実している。これには農村医学界が果たした役割は大きいが、死亡事故の防止は安全管理の徹底が第一だ。農業災害学会は「安全をつくる」学問だと考えている。農村医学界の片手間ではできない。また、事故撲滅には産官学の連携が必要だ。
◆「注意しろ」は禁句
これまでの安全管理は「注意力」が結論だった。つまり、危険を避けるため「注意しろ」というだけだった。学者なら「注意」の抽象論でもいいかもしれないが、注意して事故が起こったらどうするのか。「注意しろ」は“禁句”にしてほしい。
作業手順に問題があれば修正し、人員配置なども、現実的に提案する必要がある。これは人を使い経営者の責任である。経営者には安全配慮義務がある。
今回、学会の顧問になっていただいた元・鹿島建設の専務の大橋欣治さんは建設会社の労災対策の専門家だ。今度これを農業に生かしていただく。東京農業大学も番である。大学は学問のための学問になってはいけない。
東京農大の初代学長の横井時敬先生は「稲のことは稲に聞け」と、“実学”の重要性を唱えられた。「農業のことは農業に聞け」ということである。
危険は現場で働く労働者が一番よく知っている。農作業の安全対策は農家から聞くべきである。これは、対話で引き出すことが重要だ。例えば集落営農で、みんなに集まってもらって聞きとり、問題点を引き出す。この引き出すことが教育の原点である。
ヒューマンエラーはつきものである。安全はつくりだすものであり、重要なことは、なぜ事故が起こるかを考え、これを繰り返さない安全の体制を確立することにある。事故を防ぐ対策はある。他産業はやってきた。だから事故が減っているのだ。農業で減らないのは農業関係者の怠慢と言わざるを得ないのではないか。
◆安全運動がJAと組合員の絆強める
労災加入は就農者の5%に過ぎない。認定農家でも50%前後だ。いつまでも中身のない「注意しろ」と言っていても意味がない。具体的に指示すべきだ。「具体的に考え、実証的に説明する」。そして、「事故は経営者の責任だ」ということを、組織の責任者は認識しなくてはならない。
不安定な作業者の行動、不安定な作業環境、そして安全管理の欠陥、これが農作業事故の背景だが、もう一つ忘れてならないことは機械の欠陥だ。つまり構造、設計上のミスなどである。おの点で、中古農機のリースにも問題がある。
学会は、リスクアセスメント(危機管理)を全農家に普及させるため、モデル地域を設けて、普及させたい。JAはこれを運動として展開してほしい。これが農協と組合員の絆を強めることにもつながるものと期待している。
(日本農業労災学会創立総会における発起人代表としてのあいさつのから)
(関連記事)
・日本農業労災学会発足へ 4月8日、都内で(2014.04.03)
・農作業死亡事故減らせ 地域の取組みを全国に(2014.03.04)
・最優秀賞にJAえちご上越 農作業の危険改善(2014.02.05)
・農作業事故防止の推進会議 2月、都内で(2014.01.30)
・地域農業システムづくりへ、JAの役割とは(2013.12.06)
重要な記事
最新の記事
-
 米 4割の銘柄で下落 25年産米相対取引結果2026年1月20日
米 4割の銘柄で下落 25年産米相対取引結果2026年1月20日 -
 【浜矩子が斬る! 日本経済】タコ市首相の野望がもたらした電撃解散を許すまじ 「国家経営?」怖い勘違い2026年1月20日
【浜矩子が斬る! 日本経済】タコ市首相の野望がもたらした電撃解散を許すまじ 「国家経営?」怖い勘違い2026年1月20日 -
 JAたまな青壮年部玉名支部が最優秀賞 JA青年組織手づくり看板全国コンクール2026年1月20日
JAたまな青壮年部玉名支部が最優秀賞 JA青年組織手づくり看板全国コンクール2026年1月20日 -
 【全中教育部・オンラインJAアカデミー】育成は"人としての成長"を重視 風通しのいいチーム作りを 東京ヤクルトスワローズ前監督・高津臣吾氏2026年1月20日
【全中教育部・オンラインJAアカデミー】育成は"人としての成長"を重視 風通しのいいチーム作りを 東京ヤクルトスワローズ前監督・高津臣吾氏2026年1月20日 -
 コメどころ秋田で行われた2つの講演会【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月20日
コメどころ秋田で行われた2つの講演会【熊野孝文・米マーケット情報】2026年1月20日 -
 茨城産アンデスメロン使用「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」新発売 JA全農2026年1月20日
茨城産アンデスメロン使用「メイトー×ニッポンエール 茨城産メロンラテ」新発売 JA全農2026年1月20日 -
 2月3日は大豆の日「国産大豆商品プレゼントキャンペーン」開催 JA全農2026年1月20日
2月3日は大豆の日「国産大豆商品プレゼントキャンペーン」開催 JA全農2026年1月20日 -
 新技術「スマート飽差制御」いちご「さぬき姫」の収穫量を18.5%向上 農研機構2026年1月20日
新技術「スマート飽差制御」いちご「さぬき姫」の収穫量を18.5%向上 農研機構2026年1月20日 -
 【役員人事】三菱マヒンドラ農機(1月14日付)2026年1月20日
【役員人事】三菱マヒンドラ農機(1月14日付)2026年1月20日 -
 令和7年度 JA広報大賞受賞 JA晴れの国岡山2026年1月20日
令和7年度 JA広報大賞受賞 JA晴れの国岡山2026年1月20日 -
 農閑期に集い、学ぶ「2026いいづなリンゴフォーラム」開催 長野県飯綱町2026年1月20日
農閑期に集い、学ぶ「2026いいづなリンゴフォーラム」開催 長野県飯綱町2026年1月20日 -
 日本製紙 秋田工場に国内最大のエリートツリー「秋田閉鎖型採種園」開設2026年1月20日
日本製紙 秋田工場に国内最大のエリートツリー「秋田閉鎖型採種園」開設2026年1月20日 -
 宮城県の日本酒特化型オンラインショップ「MIYAGI SAKE MARKET」オープン2026年1月20日
宮城県の日本酒特化型オンラインショップ「MIYAGI SAKE MARKET」オープン2026年1月20日 -
 3代目「いちごクラウン」いちご王国・栃木の日記念イベントで初披露 栃木トヨタ2026年1月20日
3代目「いちごクラウン」いちご王国・栃木の日記念イベントで初披露 栃木トヨタ2026年1月20日 -
 「松江茶の湯文化のアフタヌーンティー」開催 松江エクセルホテル東急2026年1月20日
「松江茶の湯文化のアフタヌーンティー」開催 松江エクセルホテル東急2026年1月20日 -
 日本生協連など「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠協賛2026年1月20日
日本生協連など「第28回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会」に冠協賛2026年1月20日 -
 東北唯一の公立農林業系専門職大学 初の海外実習でグローバル人材を養成 山形県2026年1月20日
東北唯一の公立農林業系専門職大学 初の海外実習でグローバル人材を養成 山形県2026年1月20日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日 -
 鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日
鳥インフル ブラジルからの家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月20日 -
 静岡市・久能山「石垣いちご」1月中旬からいちご狩りが本格開始2026年1月20日
静岡市・久能山「石垣いちご」1月中旬からいちご狩りが本格開始2026年1月20日