生産資材:JA全農がめざすもの
【JA全農がめざすもの】「生活」がもっとも重要な事業になる 生活リテール部・高崎淳部長インタビュー2014年11月26日
・葬祭・配置家庭薬
・Aコープ
・ららぽーと和泉に出店
・「全農ブランド」商品
地域のくらしへの貢献と国産農畜産物の販売力強化、この2つが全農生活リテール事業の大きなテーマだと高崎部長は強調する。そして同部が担当する各事業について、いま何をするかを具体的に語った。
◆葬祭・配置家庭薬 価格訴求ではなく「満足が残る」価値の提案を
 「中期3か年計画」がスタートした昨年度、これまでの「生活部」から「生活リテール部」に機構改革を実施した同部が担当する事業は、従以前から取り組んでいる葬祭事業、配置家庭薬事業、食材宅配事業、共同購入事業そして一般消費者向け国産農畜産物などを販売する店舗事業やJAタウン、くらしの宅配便といったネット販売、そしてこうした事業に商品を開発・提供する事業など多岐にわたる。
「中期3か年計画」がスタートした昨年度、これまでの「生活部」から「生活リテール部」に機構改革を実施した同部が担当する事業は、従以前から取り組んでいる葬祭事業、配置家庭薬事業、食材宅配事業、共同購入事業そして一般消費者向け国産農畜産物などを販売する店舗事業やJAタウン、くらしの宅配便といったネット販売、そしてこうした事業に商品を開発・提供する事業など多岐にわたる。
ところが、これらの事業を取り巻く環境は大きく変化してきている。その変化にどう対応するのか。「変わらなければいけない部分と変えてはいけない部分がそれぞれの事業にある」と高崎部長は考えている。その具体例として葬祭事業をあげて説明してくれた。
葬祭事業は、2050年まで「死亡人口」が増加し、市場が拡大していく分野だとみられていることから、異業種も含めて「市場参入が拡大し、競争がどんどん激化してきている」。あわせて「同質化競争」から「価格競争」も進展しつつある。
一方で施主側の考え方も大きく変化し、特に、いままでの葬儀のやり方や形が変化しつつあり、「家族葬」等小規模葬が増えている。極端なケースでは、ご遺体を直接火葬場に運んで、火葬場で「最後のお見送り」をする「直葬」というのもある。だが、この直葬をした家族が葬儀後「直葬はこんなに寂しいものだったのか」と後悔することも多い。また、家族葬を200人、300人の葬儀をする大規模な会場で行うのも寂しく、家族葬にふさわしい空間の提供が必要になる。
時代の要請に応えながら、葬儀後に「しっかりとお見送りができた」と「満足が残る」サービスを提供していくことが大事ということだ。
配置家庭薬についても、地方では高齢化にともなう人口減少で、事業として成長し続ける状況にはない。だが、赤字だからと撤退することは簡単だが、いま現在この配置家庭薬を使っている人とっては必要なものだ。そうしたなかでどう事業を継続していくか「重要な局面にある」。
これからも配置家庭薬を利用する方は、「食品同様買物弱者需要」と「明日も健康で1日でも長生きしたいというセルフメディケーション需要」だといえる。そうしたニーズに応えるには、薬だけではなくサプリメントもあるが、飲み下しやすい介護食品や介護用品など品揃えの幅を広げ「今日の健康、明日の健康へ」という商品提供を考えていくことではないかと高崎部長は考えている。
つまり、時代が変わり、事業のスタイルが変わるなかでも、「一定の満足を得てくらしていけるような環境をどう作っていくか」ということだ。
(写真)
高崎淳生活リテール部部長
◆Aコープ 競争から連携・提携の時代に
 それは国産農畜産物の販売拠点である店舗事業(Aコープ)にもいえる。
それは国産農畜産物の販売拠点である店舗事業(Aコープ)にもいえる。
JA組合員がくらす地域の多くでは人口が減少しており、事業として成り立たなくなった多くの業者が撤退している。だからAコープも撤退していいのか。そこにも組合員のくらしがあるから、撤退するわけにはいかない。それではどうやって残すのか。そこにはいくつかの選択肢があるという。
JAグループの力だけで残せるところはもちろん残すのだが、そうではない地域では他社と連携する「ビジネスマッチング」で残すという方法をとっている。
ライフラインとして残す場合はYショップと提携した小規模店舗。概ねこれで食生活が賄えるというミニスーパースタイルは先日提携協定を結んだ全日食と提携。ロードサイドで24時間営業という制約はあるがコンビニのファミリーマートとAコープが合体したスタイルなどがすでに実現している。 昔は経済が右肩上がりで「パイが大きくなっていたので、競争社会でもそれなりに存続する可能性が高かった」。だが、現在は市場が縮小していく。そのなかで競争して共倒れをして、強いところが一つ残るのか。それとも互いに連携・提携できるところは手を結び、互いに存続できる道を考えるのか。どちらを選択するのかが問われているという。
昔は経済が右肩上がりで「パイが大きくなっていたので、競争社会でもそれなりに存続する可能性が高かった」。だが、現在は市場が縮小していく。そのなかで競争して共倒れをして、強いところが一つ残るのか。それとも互いに連携・提携できるところは手を結び、互いに存続できる道を考えるのか。どちらを選択するのかが問われているという。
全農は後者を選択したということだ。「もちろん競争するところは競争するが、互いの良さを活かして地域の貢献につながる活動をするのが、協同組合である全農の役割」だからだと高崎部長は答えた。
(写真)
「産地が見える国産農畜産物の販売拠点」JA全農ファーマーズの店内(上)と店頭ロゴ看板
◆ららぽーと和泉に出店 大都市圏に販売拠点を築く
 こうした連携・提携とは異なるビジネスマッチングが最近実現した。三井不動産の「ららぽーと和泉」(大阪府和泉市、10月30日オープン)に、JAグループの機能を結集して総合力を発揮する新業態の店舗「JA全農ファーマーズ」を、Aコープ会社である(株)エーコープ近畿が出店したことだ。
こうした連携・提携とは異なるビジネスマッチングが最近実現した。三井不動産の「ららぽーと和泉」(大阪府和泉市、10月30日オープン)に、JAグループの機能を結集して総合力を発揮する新業態の店舗「JA全農ファーマーズ」を、Aコープ会社である(株)エーコープ近畿が出店したことだ。
ここには、地元のJAいずみのの協力により直売所を設置し地産地消を実現するだけではなく、JA全農青果センター(株)大阪センターが大阪府内や近畿圏の農産物を供給、さらに今週は「○○県フェア」というように全国の全農県本部などが各県の農畜産物を販売、また、全農ミート、全農チキン、全農たまご等畜産物の加工・販売をする全農グループ会社も国産原料にこだわった商品を供給するなど、「産地が見える国産農畜産物の販売拠点」だ。
この出店について高崎部長は次のように語った。
全農の機能は、生産者と消費者の懸け橋となること。消費者の多くは都市圏中心に住んでおり、全国の生産者との懸け橋機能として、国産農畜産物にこだわって販売していくAコープは、大都市圏やショッピングセンターへも出店して、その機能をしっかり担っていこうということで、ららぽーと和泉への出店は、今後の新たな展開のプロトタイプだ。
こうした展開で、組合員がくらす地域への貢献と国産農畜産物の販売力強化という二つの大きなテーマを実現していきたい。
(写真)
ららぽーと和泉へ出店の記者会見で握手する(左から)鈴木盛夫JA全農常務、島秀和(株)エーコープ近畿社長、杉本昇JAいずみの組合長
◆「全農ブランド」商品 生産者の想い・だわりを消費者へ
 もう一つ、生活リテール部の事業で忘れてはならないのが、国産原料にこだわった「全農ブランド」商品だ。昨年秋にスタートして1年。商品も163品に拡大し、生協やスーパーから注目を集めている。
もう一つ、生活リテール部の事業で忘れてはならないのが、国産原料にこだわった「全農ブランド」商品だ。昨年秋にスタートして1年。商品も163品に拡大し、生協やスーパーから注目を集めている。
「全農ブランド」は主原料の第1位、第2位は国産農畜産物しか使わないという「他のメーカーにはない立ち位置」にたって開発されている商品群で、「将来的には輸出も視野に入れている」。
外食産業における「中国鶏肉」問題のようなことは、忘れたころに必ずといっていいほど発生する。食の安全・安心問題は、永遠の課題といえるのかもしれない。そういう意味では、安全で安心な国産原料にこだわり、そのことで国内農業を支援する。さらに生産者のおいしさや栽培へのこだわりなど、作り手の心とつながる物語性が伝わる商品にしたいというのが、全農の「全農ブランド」へかける想いだという。
もう一つこだわりがある。それは、ユネスコ無形文化財にも登録され、海外で健康的だと高い評価を受けている米飯を中心とした日本の食文化・米文化「和食」を、改めてしっかりと次世代に残したいということだ。そのためには「食育を含めてしっかりと担っていく必要がある」と高崎部長は強調する。
(写真)
国産原料にこだわった「全農ブランド」商品の数々
◆変えるべきは変え、残すべきは残す
急ぎ足で全農生活リテール部の事業をみてきたが、高崎部長が常に強調してきたことは次のことだ。
20年前のスーパーに並んでいた商品といまのを比べると一目瞭然、大きな変化がある。一つは、洋風化=サラダ化だ。ホウレンソウが生で食べられるようになり、ミニトマトが全盛となり、蒸し鶏やローストビーフが売れ、刺身もカルパッチョというサラダ化現象だ。そしてトマトだけではなくハクサイなどの野菜もミニ化されてきている。
こうした時代環境の中で、生活部から生活リテール部となったいま、従来のような「プロダクトアウト」から「マーケットイン」に転換し、「変化に対応してかえるべきところは変える」とともに「必ず残さなければいけないものは、きちんと残し」、しっかりと価値提案していく。
そのことで地域の人たちのくらしと国内農業をまもっていく。それが「生活リテール部」の仕事であり、「プライドと責任感をもってやっていこう」というのが、「いまの私たちの気持ち」なのだ。とインタビューを結んだ。
これから全農のJAグループの事業の中で、「生活がもっとも重要な事業になる」という強い決意を感じさせられる時間だった。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
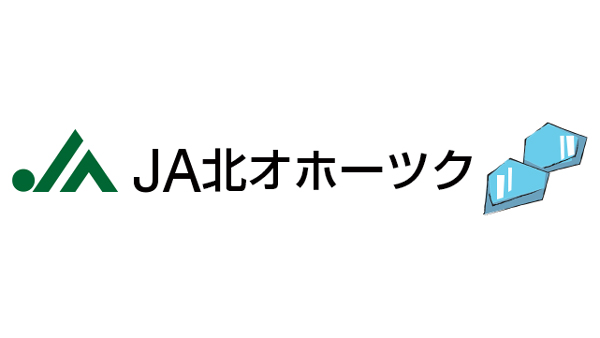 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































