JAの活動:今村奈良臣のいまJAに望むこと
第24回 農村にいかに人材を増やすか―明治大学教授 小田切徳美氏に聞く(2)―2017年7月23日
全農広報部の広報紙<JA全農ウィークリー>2017.6.12付vol.805に明治大学教授の小田切徳美君のインタビュー記事がでていて拝見し、感銘を受けたので、全農広報部長の久保田治己氏に転載の許可を頂くとともに小田切教授にも転載の許可をいただき、ここに2回にわたって全文を掲載させていただくことにした。
先週からの続きです。
前回の記事はこちら。
◆移住者に少ない専業志向まず兼業からスタート
「田園回帰」と農業との関わりをみると、意外なことかもしれませんが、移住者の中で専業的農業を志向している人はほとんどいないのが実態です。専業はリスクも高いですし。
入り方として半農半X型(注2)が大多数です。半農半Xを農水省は政策対象とは基本的に認めていません。一言で言うと兼業です。つぶそう、なくそうとしている兼業農家を増やそうとする産業政策はありえないというのが彼らの公式見解です。
これに対して半農半Xに踏み出したのが島根県です。半農半杜氏(とうじ)、半農半写真家など、Xにいろんなものが入ります。まず兼業からスタートしてくださいという新規参入対策を始めて成功していると思います。移住者の志向性にこちらの方がぴったりと合うと思います。
 地域からは17、8年前から「補助金」から「補助人」へというスローガンが聞こえてきました。1980年初頭の臨調・行革の中で、地方行政も含めて基本的には人件費は出さない、増やさないというのが基本です。補助事業には人件費が付いていない、ソフト予算が付いていないというのは当たり前でした。しかし、ある段階から人を育てるお金、支える人件費が重要だ、つまり補助金も重要だが、人に使えるお金、「補助人」という概念が必要だということになってきました。それを踏まえて地域をサポートする人、制度が必要だと政策提言して生まれたのが「地域おこし協力隊」です。3年間地城で働いてその後、多くの方が地域に残りたいということで、総務省の調査ですが56%が地域に残っています。残るためには仕事が必要で、農林業をはじめNPO、起業するなどの動きが出ています。地域おこし協力隊が人材供給の機能も果たしています。実証されてきたのは、そういったところにお金を使えば、リーダーは生まれるということです。今までお金を使っていなかったこともあり、リーダーが生まれなかった、リーダーはいても行政職員やJA職員ぐらいでした。逆に言えばそういったところには人が残る人件費が出ていて、リーダーとして活躍できていたわけです。人材供給を支える仕組みさえあれば、リーダーは生まれてきます。
地域からは17、8年前から「補助金」から「補助人」へというスローガンが聞こえてきました。1980年初頭の臨調・行革の中で、地方行政も含めて基本的には人件費は出さない、増やさないというのが基本です。補助事業には人件費が付いていない、ソフト予算が付いていないというのは当たり前でした。しかし、ある段階から人を育てるお金、支える人件費が重要だ、つまり補助金も重要だが、人に使えるお金、「補助人」という概念が必要だということになってきました。それを踏まえて地域をサポートする人、制度が必要だと政策提言して生まれたのが「地域おこし協力隊」です。3年間地城で働いてその後、多くの方が地域に残りたいということで、総務省の調査ですが56%が地域に残っています。残るためには仕事が必要で、農林業をはじめNPO、起業するなどの動きが出ています。地域おこし協力隊が人材供給の機能も果たしています。実証されてきたのは、そういったところにお金を使えば、リーダーは生まれるということです。今までお金を使っていなかったこともあり、リーダーが生まれなかった、リーダーはいても行政職員やJA職員ぐらいでした。逆に言えばそういったところには人が残る人件費が出ていて、リーダーとして活躍できていたわけです。人材供給を支える仕組みさえあれば、リーダーは生まれてきます。
◆過疎地域を支える JAの関わりに期待
全国を回っていますが7対3で西日本が多いです。西日本は高齢化が進んでいます。大ざっぱに言えば西日本から資本主義が発達し、経済が発展することで人の流動性が高まり、そのことで過疎が進んでいます。「過疎」は島根県石見地方で生まれた造語です。露骨な言葉を使ってしまえば、衰退や解体が激しいところです。こうした地域では反作用が生まれるように、新しい動きが出ています。移住する若者の中には、高い意識を持ち最先端部で地域を動かす新しいタイプの人が出てきています。島根県の海士町(あまちょう)、離島ですが、二、三百人の移住者がいます。地域の高校の魅力化プロジェクトに取り組んだり、漁業で冷凍の新しい仕組みを使って流通させたりと革新的な活動が生まれ、地域を変革する人に成長しています。地域課題に取り組んで新しいビジネスを生み出し、必ず都市と農村をマッチングし、交流に乗り出しています。いわば都市と農村の縁結び人ですね。
田園回帰の議論に総務省や国交省、内閣府、内閣官房のまち・ひと・しごと創生本部などは非常に積極的です。研究レベルでも促進しようとする動きがあります。しかし、残念ながら農水省はこの動きに立ち後れています。この点ばかりではなく、そもそも農水省は、「農政は産業政策と地域政策が車の両輪だ」としていますが、現実に地域政策として意識されているものは産業政策を補助するようなものばかりで、私は地域政策の「補助輪」化と言っています。
地域が人を呼ぶ、輝いた地域が人を呼ぶと言えます。輝いた地域はきちんと地域づくりをしているところに、人が集まってきます。撤退したAコープ店を引き受けて、地域で買い物弱者に対応している例があります。JAは地域課題の解決に一枚かんでほしいと思います。そのようなお店でも、仕入れはネットワークのあるAコープを利用してる例があります。県本部、JAが対応して少なくとも買い物弱者に対応できると思います。JAが地域づくりのコーディネーターとして関わることも考えられます。地域と関係を持たないことの方が不自然です。移住の理由は多様化していますが、いざと言うときに医療が整っていることが最低限の条件です。その点で厚生連病院は頑張っていると思います。
【ことば 解説】
注1-地域おこし協力隊
2009年にできた総務省の制度。1年以上3年以下の期間、処遇は地方自治体によりさまざまだが、非常勤の公務員として任用や地方自治体と委託契約を結ぶ場合などがある。住民票を移し地域で生活し、各種の地域協力活動を行う。活動費として自治体により違いはあるが報酬が出る(総務省は隊員1人につき、報償費等上限200万円を含む、最大400万円を財政支援している)。現在、およそ700の地方自治体で活躍している。
注2-半農半X
京都府綾部市在住の塩見直紀氏が1990年代半ばから提唱してきたライフスタイル。自分や家族が食べる分は小さな自給農でまかない、残りの時間の「X」を自分のやりたいことをする生き方。島根県は2010年から、農のある暮らしを実践しながら兼業で必要な現金収入を確保するUIターン者の支援事業をスタートさせた。対象となるのは県外からのUIターンで65歳未満の人。就農前研修経費や定住定着助成事業、半農半X開始支援事業(施設整備の経費助成)がある。半農半看護、半農半介護、半農半保育、半農半蔵人(酒造りの蔵人)などを提案し、受け入れる病院・診療所、介護施設、保育園、酒造会社などを紹介している。
【プロフィール】
おだぎり・とくみ
1959年、神奈川県生まれ。東京大学農学部卒業後、85年東京大学大学院農学系研究科農業経済学専攻修士課程修了、88年同博士課程単位取得満期退学。94年東京大学博士(農学)。高崎経済大学助教授、東京大学大学院助教授を経て、2006年から現職。『農山村再生の実践』(農山漁村文化協会)、『農山村は消滅しない』(岩波新書)など著書多数。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
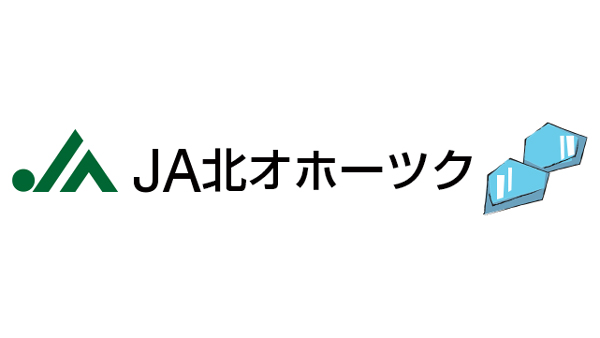 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































