JAの活動:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画
【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】中小農家の減少食い止め持続発展を 八木岡努JA水戸代表理事組合長2020年4月13日
新たな食料・農業・農村基本計画が3月に閣議決定された。今後10年の農政の指針となる。JAcom農業協同組合新聞では地域を担うJAの現場から考える基本計画についてJAトップ層に提言してもらう。JA水戸の八木岡努組合長は中小農家の減少に歯止めをかけ農業生産力の底上げを図るべきだと提言する。
 八木岡努 JA水戸代表理事組合長
八木岡努 JA水戸代表理事組合長
◆食料の重要性 国民理解を 今回5年ぶりに見直された食料・農業・農村基本計画では食料自給率目標を前回と同水準に設定しましたが、現状では37%と低迷しており、今後10年で45%に上げるためにどのような道すじを立てていくかが課題であると考えます。
今回5年ぶりに見直された食料・農業・農村基本計画では食料自給率目標を前回と同水準に設定しましたが、現状では37%と低迷しており、今後10年で45%に上げるためにどのような道すじを立てていくかが課題であると考えます。
今回、示された食料自給率目標は、「供給熱量ベース」と「生産額ベース」に加えて新たに設定された「飼料自給率」があり、その3つの総合食料自給率の向上を図るとしていますが、分かりづらいのが正直な感想です。ともあれ今後、食料自給率を上げていくには、国民全員が意識して取り組む必要があると考えています。
ライフスタイルの変化により国民の食生活は大きく変化し、一部の消費者と生産者にニーズの相違が生じております。現在の食品産業は外食や中食が増え、それに対応するため安定供給体制が必要であり、農地の集積や集約化が進められております。そうしたなか、農業法人などの大規模経営体は増加傾向ですが、国内の農業産出額としては減少しています。農業全体の底上げを図るためには、多数を占める中小規模農家数減少を食い止め、農業の持続的な発展が重要で、その取組みこそが今後の単協のやるべきことなのではないかと考えています。
国連では2019年からを家族農業の10年と定めて、食料安全保障確保に大きな役割を果たしている家族農業に係る施策の推進・知見の共有等を求めています。私は大規模農業と家族農業どちらかに力を入れるのではなく、それぞれすみ分けを図った農業支援をしていきたいと考えています。それにより農業・農村の発展、国内食料の安全保障確保、さらには食料自給率の向上につながると考えています。
◆コロナ禍をターニングポイントに
では、今後のJAとしての取組みとしては、前述のとおり食品産業は食の外部化・簡便化が今後もさらに進んでいくことが予想され、そのためには価格や量も含め安定供給が求められていきます。そのような需要には大規模農業がその部分を担っていくことになると考えています。JAとしても販売力や資材コスト低減の強化を図り、産地としてのブランド力向上支援、販路拡大、契約栽培による安定的な農家経営の支援強化を図っていきたいと考えています。
そして家族農業や新規就農者に対しては、営農技術指導、実需者ニーズを踏まえた作物提案等の営農指導を強化していき、地産地消型流通として学校給食への農産物供給の推進や、GAP導入などによるブランド力強化を図るほか、税務記帳代行などの事務軽減などの支援を強化していきたいと考えています。
また、近年EUをはじめとする海外では有機農業に対する関心が高まり、栽培面積も飛躍的に伸びています。正直、日本はその点については遅れていると言わざるを得ない状況です。日本から輸出される農林水産物・食品は「ジャパンブランド」というブランド力で注目を集めています。しかし国内農業はオーガニック種子が入手困難であることやコストと手間がかかるという理由で有機農業を手掛ける農家が少ないのが現状ですが、海外では健康志向の高まりから有機農業に注目が集まっていて、今後、輸出に関しても有機農業がトレンドになると考えてられます。国内の意識も確実にそちらにシフトしていくと予想しています。私たちの地域でその農業形態にいち早く取り組むことで、農家の所得向上や農業の発展に結びつければと考えています。
そして現在、国内の食料事情は種子法の廃止や種苗法の改正、農薬の残留基準の見直しなど、このままでは安全安心な世界に誇れるジャパンブランドとは言えない状況になってしまうのではないかと危惧しています。ゲノム編集など新たな技術も今後増えてくるでしょう。食べることは生きること、食料に安全性の関心が薄れている現代で、将来の日本を考えた時に食料の重要性を一人一人が考えることが、農業・農村の振興に繋がり、自給率は自ずと向上すると思います。
今回コロナウイルスの影響で、諸外国は自国の食料を守るために輸出を制限する方針が報道され始めました。即座に国内食料には影響はないとは言われておりますが今後どのようになるかは不透明です、もし長期的に輸入が制限された場合、自給率の低いこの現状で起こる影響は計り知れません。このような状況の時にこそ国内食料事情をすべての国民が真剣に考える必要があり、今後の農業のターニングポイントになる時期なのではないかと思います。
(関連記事)
・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】食料安保の確立へ 早期実践を 中家徹JA全中会長
重要な記事
最新の記事
-
 米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日
米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日 -
 創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日
創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日 -
 花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日
花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日 -
 どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日
どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日 -
 劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日
劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日 -
 露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日
露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日 -
 徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日
徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日 -
 長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日
長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日 -
 新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日
新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日 -
 佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日
佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日 -
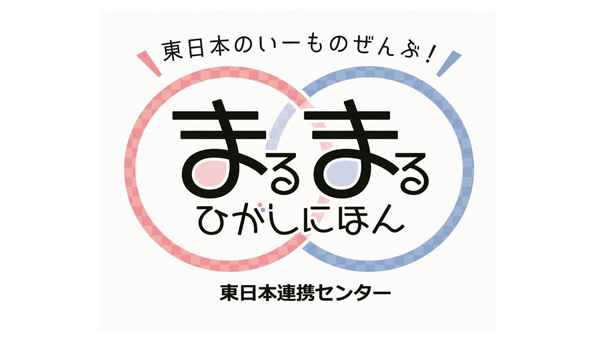 まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日
まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日 -
 日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日
日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日
人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日 -
 住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日
住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日 -
 埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日
埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日 -
 熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日
熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日 -
 外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日
外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日





































































