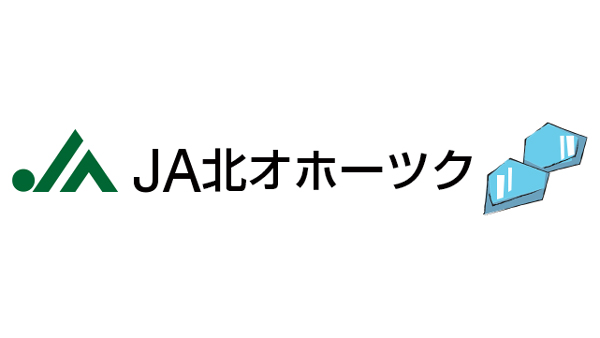JAの活動:第64回JA全国青年大会特集
【寄稿】若さと協同の力で切り拓け農業新時代【村上光雄・JA三次元代表理事組合長】(前編)2018年2月13日
いつの時代でもそうであるかもしれないが、農業の将来展望をすることは難しい。しかし今ほど難しい時代はないのではないかと思われてならない。昨年秋の総選挙で市内を隈なく走り回った。確実に耕作放棄地が拡大している。安倍農政になってからそれは加速さえしている。そして空き家も碓実に増加し、5年先のことを想像するとぞっとする。それもそのはずである。食料自給率は38%と低下傾向にあるのに更に追い打ちをかけるように国内市場開放の連鎖で、一体どこまで低下すれば気がすむのか、また食糧安全保障ということにいつになったら気が付くのかと、あきれてものが言えない。そのような状況では農業の将来展望など開けるわけもなく当然の成り行きということになってしまうが、果たしてそれでいいのであろうか? また農業には本当に将来展望が持てないのだろうか? 青年部盟友のみなさんと一緒に考えてみることにする。
◆農地は誰のもの?
 私は青年部の時からずっとこの命題を考え続けてきた。それは規模拡大を考えればどうしても農地拡大に突き当たるからである。私も昭和39年東京オリンピックの年に就農して水稲十繁殖和牛経営からスタートしたが、高度経済成長による他産業の所得増大に負けないよう規模拡大による所得増大を図らなけれぱならなくなってきた。
私は青年部の時からずっとこの命題を考え続けてきた。それは規模拡大を考えればどうしても農地拡大に突き当たるからである。私も昭和39年東京オリンピックの年に就農して水稲十繁殖和牛経営からスタートしたが、高度経済成長による他産業の所得増大に負けないよう規模拡大による所得増大を図らなけれぱならなくなってきた。
当初は町内で初めての請負耕作や手づくりの牛舎による肉用牛増頭に努めてきたが、技術的にも物理的にも限界となり、400m離れた山林に100頭規模の牛舎を建築することを決断した。それからは総合資金、農地取得資金を借りることにして、あらゆる手段で土地取得に奔走した。直接飛び込むところもあれば、知人・友人に仲にはいってもらったりした。現金払いもあれば山林と山林、水田と山林との交換など、ご理解をいただいて5ha余りの土地を確保することができた。その際土地謄本を取ってみると、土地の所有者というのは意外と移動しているものだと気が付いた。ある意味では一世代30年とすれば、世代ごとに移動しているといってもいい状態である。
よくよく考えてみれば、この土地は先祖代々わが家のものと思っていた農地も、実はたまたま今私が耕作させてもらっているだけで、結局は国家的な所有物なのだと思わざるをえなくなってきた。それからは理論武装もしないまま「農地は国家的所有物であるから、基盤整備事業は全額国が負担すべきだ」と主張してきたが相手にされなかった。しかしこのことは今も続くわたしのライフワークとなった。
◆農地所有意識の変遷
ここで少し視点を変えて戦後の農業者の農地意識の変化をたどってみる。
第一期は何といっても農地改革である。不耕作の地主から耕作するすべての農民が農地を所有することになったわけで、社会的にも経済的にも画期的なことであった。しかし、その一方で農地所有の細分化が進み、農地の資産所有意識と相まって、農地の流動性は極度に低下し農地価格は高止まりとなり、オール兼業農家へと進展していった。
当時、農民運動の旗振りをしていた我らの大先輩の宮脇朝男氏は「土地は国有化を基本とし、農民に土地の所有権はいらない、農業生産のための耕作権さえ永久に確保されればよい(要約)」として「解放農地は購入するな」と説いて回っていたとのことである。そのことが当時許されたかどうかは別として、先見性のある行動に驚かされるし、いまの農地の状態を見たときどのように分析し、行動されるだろうかと考えさせられるところである。
いずれにしろ戦後農政は耕作者主義による自作農創設により食糧確保と農村社会の安定を確保することが出来た。そしてわが国経済が安定し拡大していくのにつれて農業分野でも生産性が議論されるようになり、基盤整備事業が進められることとなった。
これが第二期の意識改革で、これまで自分の農地は最良で、先祖代々引き継いだもので絶対に動くことはないと固く信じ込んできた農地がずたずたになるのである。私の集落では、私が責任者となり昭和52年度事業で実施した。ブルドーザーが到着したらまず畦畔を取り壊した。何故なら畦畔は農地の絶対不可侵の境界であり、もめ事・紛争の元である。これを取っ払ってしまえば所有者もあきらめざるをえなくなり、これまでの農地に対する未練もなくなるわけである。
あとは農地の配分であるがこれがまた一苦労、私の集落ではそれまでにかなり交換分合をしていたのでスムーズにできたが、どの地区でもかなりもめたものである。ともかく農地は不変不動のものであるとの固定観念が破れたことは大きな意識改革であった。
次に第三期は、昭和50年の利用増進事業の導入による利用権の設定である。ここで農地の所有権と利用権が分離というか、所有権はそのままで利用権の設定が限定付きではあるが認められる事となった。
そして、いまでは利用権設定なしには農地の維持管理ができなくなってきた。つまり農地は耕作者が所有するもので一体であったが、これによって所有者と、耕作者が別々のものとなったのである。そして、いまや第四期に突入して、みんなで耕作する時代へと意識改革が迫られていると位置づけられる。
この記事の続きは、若さと協同の力で切り拓け農業新時代【村上光雄・JA三次元代表理事組合長】(後編)をご覧ください。
重要な記事
最新の記事
-
 静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日
静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -
 25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日
25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -
 (432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日
(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -
 【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日
【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -
 長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日
長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -
 【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日
【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -
 第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日
第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -
 【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日
【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -
 宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日
宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -
 静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日
静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -
 静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日
静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -
 システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日
システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -
 神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日
神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日 -
 「幻の卵屋さん」多賀城・高知の蔦屋書店に出店 日本たまごかけごはん研究所2025年4月25日
「幻の卵屋さん」多賀城・高知の蔦屋書店に出店 日本たまごかけごはん研究所2025年4月25日 -
 毎日新しいおトクが見つかる「Kuradashi公式アプリ」10万ダウンロードを突破 クラダシ2025年4月25日
毎日新しいおトクが見つかる「Kuradashi公式アプリ」10万ダウンロードを突破 クラダシ2025年4月25日 -
 夏を先取りジュース「そのまんまスイカ」果汁工房果琳などで25日から販売2025年4月25日
夏を先取りジュース「そのまんまスイカ」果汁工房果琳などで25日から販売2025年4月25日 -
 10事業所の使用電力 2025年までに実質再生可能エネルギー100%に切り替え キユーピー2025年4月25日
10事業所の使用電力 2025年までに実質再生可能エネルギー100%に切り替え キユーピー2025年4月25日 -
 「ポリビニルアルコール」価格改定 5月16日納入分から値上げ デンカ2025年4月25日
「ポリビニルアルコール」価格改定 5月16日納入分から値上げ デンカ2025年4月25日 -
 老舗の目利きを活かしたジュースやスイーツ「キムラフルーツ 西宮店」リニューアルオープン2025年4月25日
老舗の目利きを活かしたジュースやスイーツ「キムラフルーツ 西宮店」リニューアルオープン2025年4月25日 -
 中河原工場で使用の全電力を実質再生可能エネルギーに切り替え サラダクラブ2025年4月25日
中河原工場で使用の全電力を実質再生可能エネルギーに切り替え サラダクラブ2025年4月25日