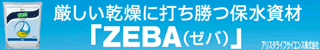【クローズアップ 続・基本計画】自給率 国民的議論をすべき-基本計画の見直し2019年11月14日
食料・農業・農村基本計画の見直しを議論している農政審企画部会が11月12日に開かれ、食料自給率と食料自給力をテーマに現状の検証と課題、新たな基本計画での自給率目標設定の考え方などを議論した。議論では自給率目標の設定は国としての施策の方向を明確にするために必要であることや、国民的議論をして理解を深めるべきだなどの指摘があった。
 12日の農政審企画部会
12日の農政審企画部会
◆農地維持が課題
現行の基本計画では令和7年度に食料自給率をカロリーベースで45%、生産額ベースで73%に引き上げることを目標にしているが、平成30年度でそれぞれ37%、66%となっている。また飼料自給率も40%への引き上げが目標だが、25%にとどまっている。
とくにカロリーベース自給率は基準年(平成25年)の39%を下回って推移している。
食料自給率が低下してきた背景としては、自給率の高い米の消費が減少するなか、自給率の低い畜産物などの消費が増加し、それに国内生産で対応が困難なものが増えたことが要因と農水省は分析している。
政策的に生産振興を図ってきた小麦、大豆、新規需要米の国内生産増加はカロリーベース自給率の上昇には0.8ポイントの寄与にとどまり、一方、米の消費は継続的に減少し▲3.4ポイントの寄与となっている。
企画部会で中家徹JA全中会長は自給率が37%と低迷している要因について検証する必要があることを強調した。
農水省は自給率低下の要因に食生活の変化を挙げるが、生産基盤の弱体化によって国産が供給できなくなっていることが大きいのではないかと提起した。また、農地の減少も生産基盤の弱体化につながっているが、「なぜ農地が荒廃地化するかまで検証が必要だ」と指摘するとともに、農地中間管理機構の機能についても評価することが必要だとした。
また、農水省は輸出を伸ばすことも重要だとするが中家会長は「(食料自給という)本来の趣旨とは違うのではないか」と疑問を呈し、むしろいかに輸入が増えているかをデータを示して検証すべきではないかと指摘した。そのほか国内生産対策では小麦、大豆の需要が高まっていることから「強い政策が必要」だと述べるとともに、食料、農業についての国民理解を広めるために、「国民的議論の喚起、ではなく国民的議論をすべきだ」と強調した。
全国農業会議所の柚木茂夫専務は日本型食生活を望ましい姿としてもっと周知し米の生産と消費に改めて力を入れるべきではないかと述べた。また、農地を維持するために「採算が合わなくても農家に手を入れてもらうような施策をいかに国民理解のもとでつくるかも検討すべき」と提起した。
中谷朋昭横浜市大データサイエンス学部教授は農地維持に限界があるなか、日本が国として自給力を維持していくには単収の向上、外国人労働者も含めた農業者の増加、スマート農業など技術革新もふまえて計画を打ち出すべきではないかと述べた。
柏染谷の染谷茂代表取締役は現在の基幹的農業従事者145万人が10年後には70万人になるなど「それで自給力が維持できるか不安」とし、国民への供給食料を国内農地でまかなっているのは3割にも満たない計算になるとして「国民に実態を理解してもらう取り組みが必要だ」と強調した。
◆需要の変化に対応を
キッコーマンの堀切功章社長は「需要の変化を見極める必要がある」として弁当や総菜など増える中食に国産農産物をどう供給するかという考え方が大切になると述べた。
カロリーベースよりも生産額ベースの自給率で示すことが重要との意見もあった。
主婦連の有田芳子会長は生産額ベースで自給率を示すことが「今の農政の姿勢にあっている」との見方を示した。日本テレビの宮島香澄解説委員も「稼ぐ力を増やしていこうという金銭的な価値も含めて目標にすべきではないか」と述べた。また、クレアファームの西村やす子代表は「生産現場は収益性を考え、消費者は美味しいものを選ぶ」のが現実と指摘し、「自給率の捉え方が人によって違う。それぞれの立場の人が何を意識して努力すべきか分かりやすい目標があったほうがいい」と話した。
一方、図司直也法政大学現代福祉学部教授は、都道府県レベルの自給率が理解されやすいとして、自給率向上のためには「風土に根ざした適地適作も大事で、それを支える地産地消が積み上がっていくことが重要ではないか」と提起した。また、世界を見れば飽食と飢餓が共存しているのが現実で、「自国の資源をしっかり活用することや、栄養バランスのとれた食を実現していくためにも、カロリーベース自給率で読み取れるところは大きく有効性はある」と指摘した。また、食料輸入の指標として、フードマイレージや食料輸入は水の輸入でもあるとするバーチャルウォーターなどを示すことも重要だと提起した。
部会長の大橋弘東大教授(公共政策大学院経済学研究科教授)は「目標を立てることは、国として施策の方向を示す意味がある。何を目標にすべきか明確にすべきだ」と強調。目標は食料安全保障や食の豊かさ、望ましい食生活などで、自給率・自給力目標はそれらを実現するための数値として議論していく必要があるなどと話した。
次回の企画部会も引き続き自給率・自給力をめぐる議論を行うとともに、農業構造の展望なども示す。
(関連記事)
・多様な農業者で生産基盤強化を-JAグループの基本政策提案(19.11.14)
・【クローズアップ・基本計画】自給率議論も本格化 地方で意見交換会も 農政審企画部会(19.11.12)
重要な記事
最新の記事
-
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日 -
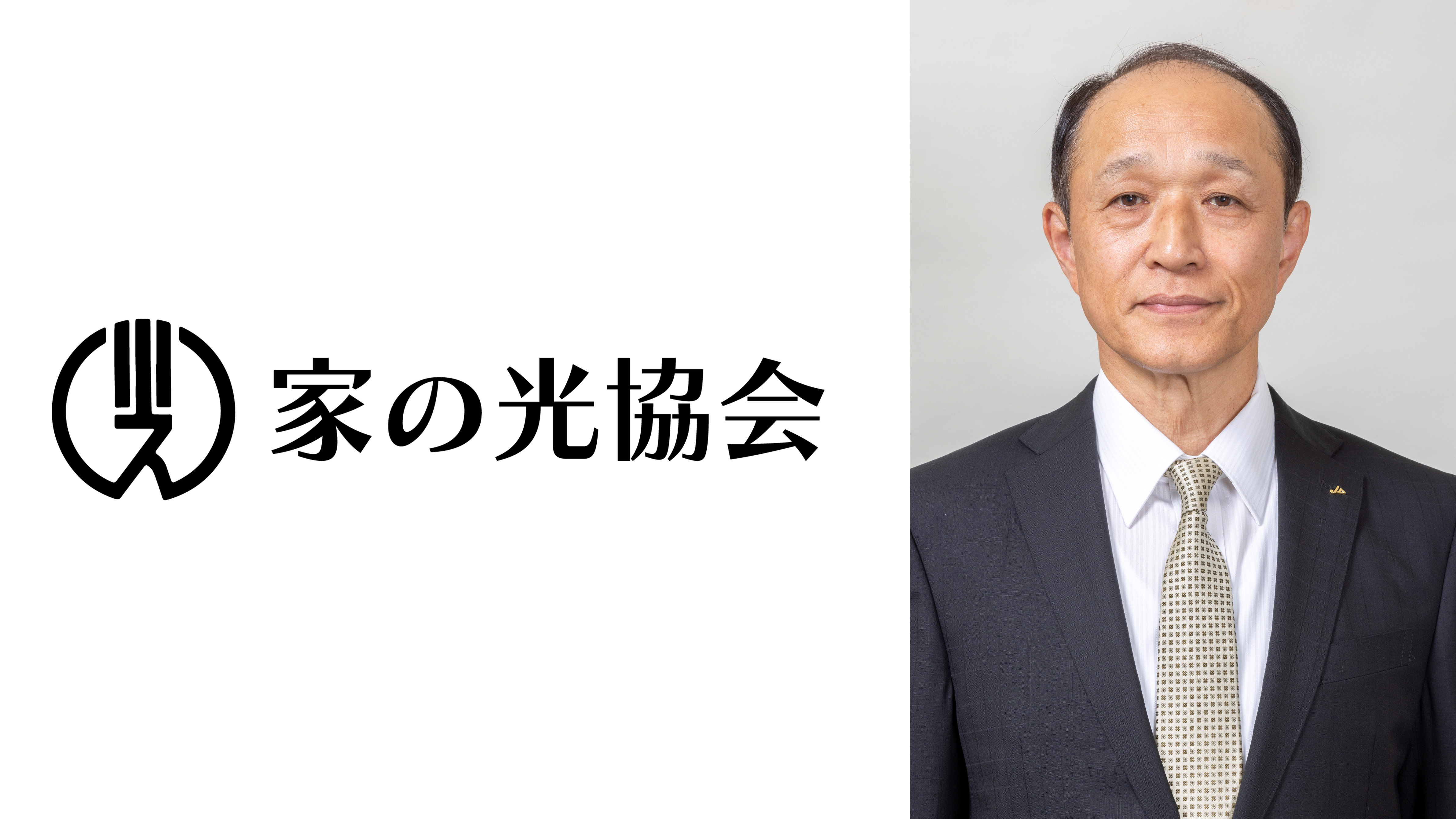 【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日 -
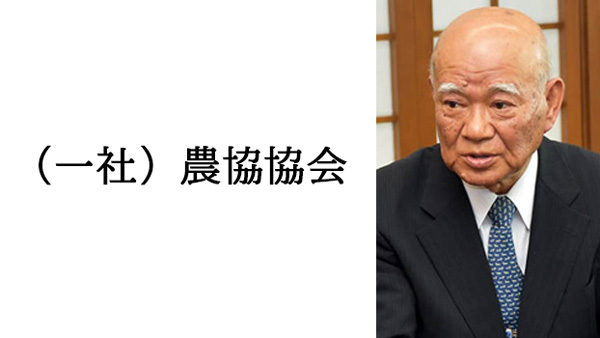 【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日 -
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日