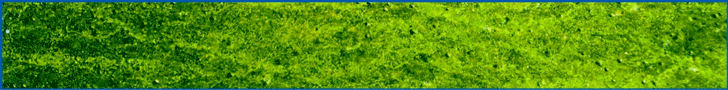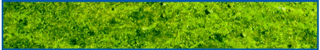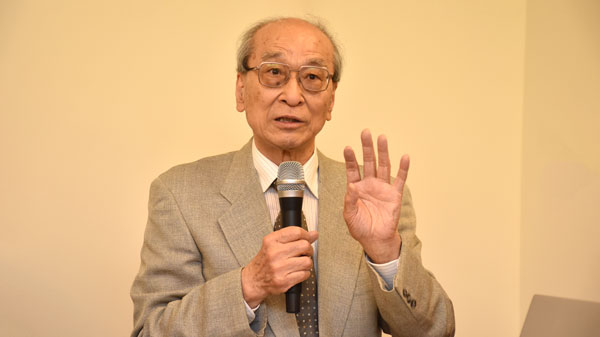農薬:いんたびゅー農業新時代
適切な診断ができる人材を育成【宇野彰一・全国農薬協同組合理事長】2017年8月9日
農薬など生産資材の生産者への販売ルートは、JAグループによる「系統」と、それ以外の「商系」ルートがある。農薬の商系ルートとして、全国の農薬卸会社が経済事業としての共同購買事業を基礎とし、個別企業を組合員とする全国農薬協同組合(全農薬)を昭和40年に設立し、全国農薬卸の窓口として経済事業、教育情報事業、組合員福祉事業などの活動を行ってきている。現在、45道府県に206の組合員で構成されている。今日の農業や全農薬の活動について、宇野彰一理事長に忌憚なく語っていただいた。
◆日本農業の繁栄は 輸出から
――日本農業についてどのようにご覧になっていますか?
 日本の農業は米国や豪州と比べると、緻密で繊細で、まさに芸術的な農業だと思います。日本農業が見習うべきはオランダです。EUに統合された時に輸出に軸足を置いて実績を築いてきているオランダです。日本国内は人口減少に伴って食市場は縮小していきますから、農産物の海外への輸出に、今まで以上に注力することが、日本農業の繁栄につながると思います。
日本の農業は米国や豪州と比べると、緻密で繊細で、まさに芸術的な農業だと思います。日本農業が見習うべきはオランダです。EUに統合された時に輸出に軸足を置いて実績を築いてきているオランダです。日本国内は人口減少に伴って食市場は縮小していきますから、農産物の海外への輸出に、今まで以上に注力することが、日本農業の繁栄につながると思います。
日本の農業は水田農業一つをとっても品質や収量はかなり高いレベルにあり、出来上がった農産物はまさに芸術品といえます。そうした良質な農産物は海外でもきっと高い評価を得ると思います。
そして世界的には食料難の時代ですから、日本の米や野菜、果樹はどんどん受け入れられると思います。
(写真)宇野彰一・全国農薬協同組合理事長
◆生産現場をみて具体的な提案をする
――ここ数年「農業改革」とか「農協改革」といわれ、「農業競争力強化支援法」が施行されるなどの動きがありますが、全農薬加入企業に影響がでていますか?
まだ直接的な影響はありませんが、みんな不安に感じていることは間違いないです。
「改革」や法律の制定の一番大きな目的の一つが、良質で低廉な生産資材の供給だとされています。これによって生産資材の値段が下がるということは、私たち流通業者にとっては致命的なことです。なぜなら価格に占める私たちのマージンはごくわずかですから、価格が下がれば経営的にも影響が出てくるという危機感を各社とも持っています。
――そうした危機感を持ちながら、いま農薬卸会社は何をしなければいけないとお考えですか?
現場に行って、農家のほ場を見て、問題を把握して、適正な農薬は何かを考え、提案することです。防除暦とか栽培暦が各地で定められていますが、農作物の生育や病害虫の発生は天候が8割です。その時々で使う農薬は変わりますから、現場に合った提案ができ、そして農家やお得意先に信頼していただける人材を育成していくことが、私たちの大切な使命だと思います。
今の時代は、省力化することが非常に大事です。とくに大規模農家では、少々価格が高くても省力化できれば結果的にはコストダウンにつながります。そうした薬剤や防除手段の提案は、非常に意義があることだといえます。
――コスト低減は資材価格を下げることだけではなく、上手に効率的に省力的に使うなどトータルで考えていく...
農水省のある会合で農家の方が「単純に低価格の農薬を使えばいいとは考えていない。安くても効果がなければ無駄なので、自分の生産現場にとってより良いものは何かを考えてくれることが、一番のコスト低減だ」と発言されていましたが、まさにそういうことではないでしょうか。
除草剤や殺菌・殺虫剤のなかには数年前までは効果があったけれど、抵抗性が出て効果が期待できなくなったものもありますし、抵抗性があるかないかは地域によって異なるので、提案するときにはそうした知識を持ち、判断できるかどうかも重要です。
――そういう人材を育てているわけですね。
私たちは「処方箋の書けるコンサルタント」といっていますが、病害虫診断に加え、ADIや近年設けられた急性暴露評価等の安全性についてもきちんと説明ができる人材を育てるために、非常にレベルの高い資格制度を設けています。その資格試験に合格した「農薬安全コンサルタントリーダー」という有資格者が、全国に現在79人います。この資格を持つ人材を増やしていきたいと考えています。
そして、価格だけで競争するのではなく、地元の農家やお得意先と面と向き合って対話し、正しい適切な情報ときめ細かなサービスを提供することが、私たち商系の生きる道だと考えています。
◆危惧される登録農薬「再評価」の影響
――理事長は農業資材審議会農薬分科会の委員を務められていますが、農薬取締法改訂の準備が進められ、そのなかに登録農薬の「再評価」が含まれています。この影響についてどう見ておられますか?
再評価のあり方によっては、コストがかかり農薬の価格が高騰するのではないかと危惧しています。消費税が増税された時もそうでしたが、価格が上がるとなると必要以上に購入される方がおられ、通常は十分量ある商品が不足するなど、製造・流通と生産の現場で混乱が生じる可能性があります。
もう一点は、一つの病害虫や雑草に有効な薬剤が減るのではないかという危惧です。販売量が少なくても、マイナー作物の産地ではその薬剤を大切に使っていたりしますが、再評価にコストがかかればあまり販売量が多くない薬剤は生産を中止する可能性があります。そして、有効な農薬の数が減るということは、生産現場での選択肢が減り、これまで行ってきたローテーション防除ができなくなる可能性があります。
そうなれば病害虫の抵抗性問題もどんどん加速しますし、作物をつくるうえでの植物防疫が極めて困難になると思います。
ひいては、産地が衰退することも考えられるのではないでしょうか。
ぜひ、生産現場が困らないようなものにしていただきたいと思います。
――全農薬では共同購買をされ長年にわたって取扱っている剤がありますが、これは即、再評価の対象ではないですか?
共同購買事業の中心が殺菌剤のジマンダイセンで、その他に有機りん剤、除草剤を含め現在20剤くらいを取扱っています。今回の再評価により、生産中止となる薬剤もあるのではないかと心配しているところですが、そうなると全農薬の経営にとっても大きな問題となります。
◆産地の輸出対策も支援していく
――今後の方向としてお考えになっていることは、何ですか?
日本農業は冒頭でも話したように、今後は農産物輸出が大きな活路だといえますので、先ほど紹介した「農薬安全コンサルタントリーダー」に、国と連携して輸出を支援する事業にも取り組んでもらいたいと考えています。
――具体的には...
産地が輸出をしたいと考えた時、相手国によって使える農薬や防除体系、検疫が違います。その輸出国に合わせた農薬使用などの情報提供をするといったお手伝いをさせていただこうということです。
――最後に、生産者そしてJAにメッセージをお願いします。
全農薬は「小回りの利く営業」をモットーにしていかなければいけないと思いますので、お困りのことがあれば、お近くの全農薬組合員にご相談いただくことで、問題解決につながると思いますので、ぜひ全農薬並びに組合員をどうぞよろしくお願いいたします。
(関連記事)
・技術革新で国内外の農業に貢献【小池 好智 クミアイ化学工業(株)代表取締役社長】(17.07.28)
・総合的提案でワクワクする農業を【西本 麗 住友化学株式会社 代表取締役専務執行役員】(17.04.21)
・生産者の所得向上に貢献【篠原聡明 シンジェンタジャパン(株) 代表取締役社長】(17.03.19)
・さらに深く日本の農業へ バイエル仁木理人本部長インタビュー(17.02.17)
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(135)-改正食料・農業・農村基本法(21)-2025年3月29日
シンとんぼ(135)-改正食料・農業・農村基本法(21)-2025年3月29日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(52)【防除学習帖】第291回2025年3月29日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(52)【防除学習帖】第291回2025年3月29日 -
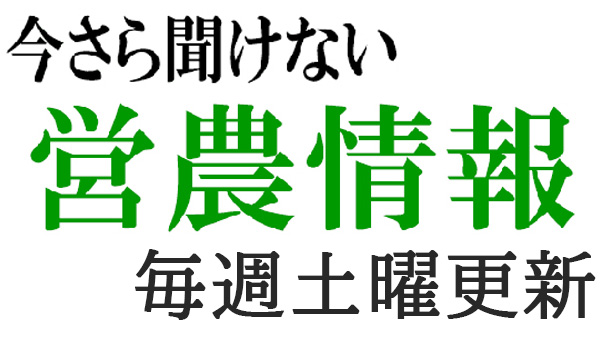 農薬の正しい使い方(25)【今さら聞けない営農情報】第291回2025年3月29日
農薬の正しい使い方(25)【今さら聞けない営農情報】第291回2025年3月29日 -
 【現地レポート】「共同利用施設」が支える地域農業とこの国の食料 JA秋田おばこ六郷CE(2)2025年3月28日
【現地レポート】「共同利用施設」が支える地域農業とこの国の食料 JA秋田おばこ六郷CE(2)2025年3月28日 -
 農協の組合員数1021万人 前年度比0.6%減 2023事業年度 農水省2025年3月28日
農協の組合員数1021万人 前年度比0.6%減 2023事業年度 農水省2025年3月28日 -
 農業構造転換 別枠予算の確保を 自民党が決議2025年3月28日
農業構造転換 別枠予算の確保を 自民党が決議2025年3月28日 -
 (428)「春先は引越しの時期」?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年3月28日
(428)「春先は引越しの時期」?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年3月28日 -
 大関と共同開発「ニッポンエール レモンにごり酒300ml瓶詰」新発売 JA全農2025年3月28日
大関と共同開発「ニッポンエール レモンにごり酒300ml瓶詰」新発売 JA全農2025年3月28日 -
 愛媛県の林野火災被災者に共済金など早期支払い JA共済連2025年3月28日
愛媛県の林野火災被災者に共済金など早期支払い JA共済連2025年3月28日 -
 県内最大級のねぎイベント! 「大分ねぎまつり2025」を開催 JA全農おおいた2025年3月28日
県内最大級のねぎイベント! 「大分ねぎまつり2025」を開催 JA全農おおいた2025年3月28日 -
 「好きがみつかるスポーツテスト」特設サイトをリニューアル 体力測定結果なしに診断 JA共済連2025年3月28日
「好きがみつかるスポーツテスト」特設サイトをリニューアル 体力測定結果なしに診断 JA共済連2025年3月28日 -
 毎月29日は「いい肉の日」限定セール開催 約360商品が特別価格 JAタウン2025年3月28日
毎月29日は「いい肉の日」限定セール開催 約360商品が特別価格 JAタウン2025年3月28日 -
 粘り強く贈答品にも 天候によって形状が変わる「相模原のやまといも」 JA相模原市2025年3月28日
粘り強く贈答品にも 天候によって形状が変わる「相模原のやまといも」 JA相模原市2025年3月28日 -
 土浦れんこんカレー 県産れんこんと豚肉がゴロッと JA水郷つくば2025年3月28日
土浦れんこんカレー 県産れんこんと豚肉がゴロッと JA水郷つくば2025年3月28日 -
 夏も冷涼な気候生かし 完熟ミニトマトで100%ジュース JA新いわて2025年3月28日
夏も冷涼な気候生かし 完熟ミニトマトで100%ジュース JA新いわて2025年3月28日 -
 【中酪25年度事業計画】生乳需給変動対策に参加、離農加速受託戸数9600台も2025年3月28日
【中酪25年度事業計画】生乳需給変動対策に参加、離農加速受託戸数9600台も2025年3月28日 -
 太陽光発電設備・蓄電池設備を活用 JA帯広大正で再エネ導入2025年3月28日
太陽光発電設備・蓄電池設備を活用 JA帯広大正で再エネ導入2025年3月28日 -
 JA三井リース Frontier Innovations1号投資事業有限責任組合へ出資2025年3月28日
JA三井リース Frontier Innovations1号投資事業有限責任組合へ出資2025年3月28日 -
 ウェブコンテンツ「社会のニーズに対応したソリューション」を公開 日本農薬2025年3月28日
ウェブコンテンツ「社会のニーズに対応したソリューション」を公開 日本農薬2025年3月28日 -
 【組織改定・人事異動】デンカ(4月1日付)2025年3月28日
【組織改定・人事異動】デンカ(4月1日付)2025年3月28日